本文
立山寺と大徹禅師(眼目)
眼目の立山寺というお寺は、今からおよそ六百年あまりもむかしに建てられたそうじゃが、このお寺ができるまでには、立山権現さまのお手助けがあったという話を知っておるかいのう。
立山寺をご開山になったお方は、大徹禅師というて、能登(石川県)の総持寺というお寺におられた、えらいお坊さまであったそうな。
 あるとき、大徹さまは越中の国へやってこられたと。そうすると、東の方に、まっ白に雪をいただいた立山連峰が見え、空には紫色の雲がたなびいて、なんともいえず神々しく、大徹さまの心をすっかりとらえてしもうた。心はその山のふもとの方へひかれて、どうにもならなんだ。
あるとき、大徹さまは越中の国へやってこられたと。そうすると、東の方に、まっ白に雪をいただいた立山連峰が見え、空には紫色の雲がたなびいて、なんともいえず神々しく、大徹さまの心をすっかりとらえてしもうた。心はその山のふもとの方へひかれて、どうにもならなんだ。
「あの山のふもとで座禅をくんでみたいものよ。」
と、大徹さまは、何かにひきよせられるように足を運ばれ、とうとうたどりついた山里の、深い静かな林の中で、ちょうどすわるのに手ごろな大石をみつけて、さっそく、その上で座禅をくみはじめられたと。
すると、そこへ、一人のみすぼらしい木こりがやってきたそうな。木こりは、大徹さまのようすに、えらく心をうたれたように、「お坊さま、どうかこのわたしにも、いっしょに座禅をくませてくだされませ。」
と、お願いをしたと。
大徹さまは、こころよう、そのたのみを受け入れられて、木こりといっしょに石の上で座禅を続けられたと。そうして七日の間、いろいろと仏さまの教えを説いて聞かせられたそうな。木こりは、心の底から大徹さまを信頼し、教えをよろこんだ。
「長い間、心に思うておったことが、今やっとかなえられそうでございます。どうかお坊さま、この香積の野に寺を建てて、仏さまの教えをひろめてくだされませ。寺を建てるに必要な材木は、わたしが用だてしましょうぞ。」
そのことばに大徹さまは、これはただの木こりではなさそうじゃ、と思うておられると、
「じつは、わたしは立山権現なのじゃ。」
と言うて、ふっとすがたが消えてしもうた。
さて、その夜のことだったと。にわかに大雨がふりだして、近くを流れる川の水がどんどんふえ、洪水になるかと思われるほどになってきたと。そのうちに、川上の方から、材木が次から次へと流れてきて、それらがみんな岸についた。よく見ると、材木の一本一本に、「立山寺」と焼き印がおしてあったそうな。
さて、またふしぎなことに、こんどは、どこからともなく、十八人のたくましい男たちが集まってきて、その材木をどんどん運び、木を刻みはじめた。男たちは大工の集団であったわけだ。
そうこうするうちに、七堂伽藍のりっぱなお寺ができあがってしもうた。つまり、立山権現さまが、大徹さまに、お寺の開山をたのまれたと言うことだろうのう。
さてそういういわれがあってできあがったお寺じゃから、大徹さまも、いっしょうけんめい、仏さまのことを、人々に説いて聞かせられた。それだもんで、里の人たちも、大徹さま、大徹さま、というて心から慕うた。そのお説教を喜ぶ声は、どこまでも広まっていって、人間ばかりか、おく山の池にすんでおった竜神の耳にまで入ったそうな。
竜神は、池の主ではあっても、人間ではないわけじゃ。竜神は、ほんとは人間のようになりとうてしかたがなかった。とうとう竜神はがまんできんようになって、思いきって大徹さまのところへお願いに行ったと。
「どうかわたしにも、人間のような心をもたせてくださりませ。」
大徹さまは、どんな者にもわけへだてはなさらなんだ。だから、竜神のねがいも、気持ちよう受け入れられた。竜神は、七日の間、いっしょうけんめいお寺に通いつづけて教えを受けたあげく、とうとう、念願の人間のすがたにかえてもらうことができたそうな。
竜神は、喜んで喜んで、どうやって大徹さまに恩返ししようかと考えぬいたすえに、池にさいているハスの糸をつむいで、りっぱな袈裟をおり、それを献上したということじゃ。
さてまた、そのころ、滝橋のおくの城房というところに、城房太郎というて、どえらい悪党がおったそうな。この者は、世の中にめいわくをかけるような悪さを、かたっぱしからやってのけ、里の人たちをふるえ上がらせておった。
そんな悪党が、大徹さまのうわさを耳にすると、
「ふん、いかに仏じゃろうと大徹じゃろうと、このわしには歯が立たんじゃろう」
と、大いばりで大徹さまにむかい、悪口のありだけふりまいたと。
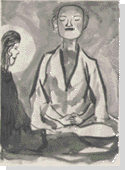 ところが大徹さまは、よい人間もわるい人間も区別なく、同じように心をかけてくださる方じゃから、城房太郎にも、やさしく仏さまのことを語って聞かせられた。はじめのうちは聞こうともせなんだ城房太郎だったが、だんだん回が重なるうちに、さしもの悪党の心もいつのまにやら大徹さまの方へかたむき、しまいには、大徹さまのお顔を見んことには、さびしゅうてたまらんようになってしもうた。お寺へいって、大徹さまのお顔をただ見ておるだけでも、心がなんとなく安まるわけじゃ。
ところが大徹さまは、よい人間もわるい人間も区別なく、同じように心をかけてくださる方じゃから、城房太郎にも、やさしく仏さまのことを語って聞かせられた。はじめのうちは聞こうともせなんだ城房太郎だったが、だんだん回が重なるうちに、さしもの悪党の心もいつのまにやら大徹さまの方へかたむき、しまいには、大徹さまのお顔を見んことには、さびしゅうてたまらんようになってしもうた。お寺へいって、大徹さまのお顔をただ見ておるだけでも、心がなんとなく安まるわけじゃ。
そのうちに、布教などで大徹さまがお寺をるすになさるようなことがあると、もうもう、心細うて、ひとりではおられんようなことになったと。このさびしさをおぎなう、何かうまい方法はないもんだろうかと、城房太郎はあれこれ思案したあげくに、ひとつのことを思いついた。それは、大徹さまのおすがたをそっくりに、木像に刻もうということじゃ。そうすりゃあ、昼でも夜でも、いつでも大徹さまといっしょにいるここちじゃ。
城房太郎は、大徹さまにおゆるしをうけると、さっそく、仏師にたのんで像を彫ってもろうた。やがて、りっぱに木像ができあがり、大徹さまも、えろうよろこばれた。そうして、ご自分の像に自ら眼を入れ、魂を入れる行事もされたそうな。大徹さまがその木像に向かって、
「大徹和尚っ。」
と声をかけられると、木像は、首をふって返事さえしたといわれておる。大徹さまの魂が、ほんとうに、木像に乗りうつってしもうたしょうこじゃろうのう。
城房太郎は、それからあとは、その木像といっしょにおれば、ちっとも、さびしいおもいはせなんだそうな。
さて、眼目のお寺は、むかしから三回も火事におうて焼け落ち、むかしの面影はさっぱりなくなってしもうたが、大徹さまの木像と、座禅をくまれたという「座禅石」だけは、今もしっかりと残っておる。大徹さまはなくなられても、そのお心は、今の世の人にも、ちゃんと受けつがれているということじゃのう。
弘法さまと護摩堂(護摩堂)
弘法大師といえば、だれでも知っている、えらいお坊さまじゃ。今から千年もむかしに、日本の国のあちこちをめぐり歩かれて、びんぼうな人たちや、こまったことの起こっている村々に、仏さまのみ教えや、いろいろな恵みをあたえてくだされたそうな。
弘法大師にまつわる伝説は、日本じゅうにたくさんあるが、この上市町にもいくつか言い伝えられているのを知っているかのう。
護摩堂の村というのは、山の中腹にある村じゃ。だから、むかしはクマやイノシシなどのけものがいっぱいおって、そいつらがわがもの顔に村の中へ出てきて、村の人たちが精出して作った、田や畑の作物を荒らしまくっておったと。村の人たちは、どうやって、けものの害を防げばいいやらと、いつも頭をなやませておったわけじゃ。
さてそのころ、諸国をまわっておられた弘法さまが、ちょうどこの村へもやってこられたと。
旅から旅へと歩いてばかりの弘法さまは、たいそうのどがかわいてがまんがならず、一けんの家の戸口にいたばあさまに、
「水を一ぱいもらえぬか。」
と所望された。
声をかけられたばあさまは、
「はいはい。それでは、くんでまいりますけに、ちょっと待っとってくだされませ。」
と言うて、いそいそと、どこへやら出ていってしもうたと。それっきり、弘法さまがいくら待っておっても、なかなかもどってこなんだ。
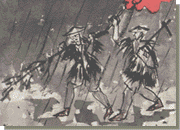 はて、どうしたことじゃろう、と弘法さまは、のどのかわきをいっしょうけんめいがまんしながら待っておられた。そうとうに長い時間がたってから、ようやく、ばあさまは水をもってあらわれたと。
はて、どうしたことじゃろう、と弘法さまは、のどのかわきをいっしょうけんめいがまんしながら待っておられた。そうとうに長い時間がたってから、ようやく、ばあさまは水をもってあらわれたと。
弘法さまは、一ぱいの水にのどをうるおし、ばあさまにお礼を言いながらも、どうしてこうもおそかったのか、そのわけをたずねられたんじゃ。するとばあさまは、申しわけなさそうに、
「はい、年よりは足がおそうて、すまんことでございます。実は、この村には水がないがでございます。水をくむには、遠い谷川まで行かんならんもんで。」
と言うた。
村からはるか下の谷川までは、八、九丁(約一キロメートル)もあると聞かされた弘法さまはおどろいて、
「それはえらい難儀をかけたのう。」
と、ばあさまをいたわりながら、手に持っておられた錫杖で、そこらへんの地面をとんとんとつかれたと。すると、ふしぎなとこに、その場所から、きれいな水が、こんこんとわき出てきたそうな。ばあさまは、弘法さまをふしおがんで、よろこんだ。村の衆も大ぜいあつまってきて、突然なできごとにたまげながらも、これからは遠くへ水くみにいかんでもいいことを、おたがいによろこび合うた。
弘法さまは、あつまった村人たちに、
「まだほかに、村でこまっていることはないかの。」
と、たずねられたと。村の衆は、これはただびとではないぞ、と、すがるような気持ちで、毎年、けものの害で苦しんでいることを、口ぐちにうったえた。
弘法さまは、さっそく、そのなやみを取りのぞいてやろうと、けもの封じの護摩をたかれたと。そのおかげで、さしも、あばれまわっておったけものたちも、なりをひそめてしもうて、それからあとは、田や畑を荒らされることも少なくなり、村の人たちは、大助かりしたそうな。村の衆は、弘法さまを大へんにあがめて、護摩をたかれた場所に、弘法堂というお堂を建て、村の名も「護摩堂」とよびならわすようになったと。
そのほかにも弘法さまは、村に、ももの木を植えることをすすめられたそうな。ももの木はいっぱい植えられて、やがてりっぱに成長し、もも林になったと。
護摩堂名所ちゃ なんにゃ名所
ももに花さく そりゃ名所
と、あとあとまで、歌にもうたわれたそうな。
むかしのはなしはそこまでじゃが、今の池の原という所が、もも林のあった所だそうな。しかし、弘法堂は、古うなったものを建てかえて、今でも村に残っているんじゃ。そのゆか下には、護摩をたかれたという、くぼみのある大きな石も残っておる。お堂のうしろの岩石のわれ目からは、夏冬をとわず、冷たいきれいな水が、今もつきることなくわき出して、時たまおとずれる人の、のどをうるおし、弘法さまの水として、だいじにされておる。また、近くには、弘法さまの足あとがついているといわれる石もあって、弘法さまの名は、けっして、わすれられることはないじゃろう。
さぁて、弘法さまにまつわるお話のついでとして、もう一つ、二つ、別な話をしようかいのう。
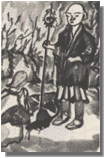 弘法さまが、あるとき、稲村という所を通られると、ある一けんの家の前に、とれたばかりのいもがおかれてあったと。あんまりうまそうに見えたもんで、その家のものに、
弘法さまが、あるとき、稲村という所を通られると、ある一けんの家の前に、とれたばかりのいもがおかれてあったと。あんまりうまそうに見えたもんで、その家のものに、
「どうじゃろ、一つごちそうしてもらえまいか。」
と、たのまれた。すると、どこやら根性のわるそうなばあさまが出てきて、
「おらっちゃの家には、石いもというて、かたぁいいもしかないがいね。あんたはんの口にちゃ、あわんですちゃ。」
と、つっけんどんに言うたと。それでも弘法さまは、
「いくらかたいというても、あんた方が食べられるのなら、わしにだって食べられぬということはないだろうに。」
と、もう一度言われたが、ばあさまは、そっぽをむいて、
「あんたはんの食べられるようなもんではないがいね。」
と、やっぱりことわってしもうたと。弘法さまは、あきらめたように、
「それほどまでにかたいいもなら、しかたがないのう。」
と言い残して立ち去られたそうな。
ところが、その後、その家にはほんとうに食べられんような、かたいかたいいもしかとれんようになってしもうたと。
もう一つ、これもにたような話じゃが、やっぱり弘法さまが蓬沢の村をたく鉢しておられるとちゅう、ある家に立ちよられて、
「わしに、小豆を少々もらえまいか。」
と言われた。すると、よくばりもののその家のおっ母は、
「おらちの小豆は、石小豆というて、かたいかたい食べられん小豆ですちゃ。」
と言うた。
「あんた方が食べておるなら、わしにも食べられると思うがなぁ。」
とおっしゃったけれども、おっ母は、どうしても聞こうとせなんだ。
「それでは、むりにとは言わぬ。」
と、立ち去って行かれたが、その家でも、それからというものは、カチンカチンにかたいやせた小豆しかとれんようになったそうな。
よくばりものとは、しかたのないものだのう。
市姫物語(上中町)
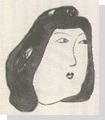 むかし、むかしのことです。ある日、上市の商人、次郎右衛門は、三日市の市場へ行った帰り道、夕やみの中で、たいそう気品の高いお姫様に出会いました。お姫様は手に梅の花を持ち、そのすがたはいかにもやさしくきれいでした。次郎右衛門は、思わず立ちどまり、しばらくぼんやりしてしまいました。
むかし、むかしのことです。ある日、上市の商人、次郎右衛門は、三日市の市場へ行った帰り道、夕やみの中で、たいそう気品の高いお姫様に出会いました。お姫様は手に梅の花を持ち、そのすがたはいかにもやさしくきれいでした。次郎右衛門は、思わず立ちどまり、しばらくぼんやりしてしまいました。
すると、そのお姫様は、次郎右衛門に、
「ここの上の方にもあらたに市場が開け、はんじょうしているそうですが、そこへ行きたいのです。わたしは市姫と申します。どうぞわたしを連れて行ってください。」と声をかけられました。
「いいですとも、お連れいたしましょう。でも道が悪いですから、そこまでわたしがおぶってさしあげましょう。」と、次郎右衛門は答えて、お姫様をせおってみますと、案外軽いように思われました。
やがて行き着きますと、お姫様は、
「ここにわたしをおろしてください。」と、おっしゃいました。そこで、次郎右衛門はせおっていたお姫様を下におろしました。
すると、なんとそれは、お姫様ではなくて大きな石でした。夜が明けて、さっそく次郎右衛門は、集まってきた人々にこの話をしますと、
「そのかたはきっと神様にちがいない。お社を建てておまつりしましょう。」
と、相談がまとまりました。そこで、三日市の方向である西向きにお社を建ててまつり、そばに梅の木を植え「市姫社」と名づけました
このようにして、市姫の神様は三日市から上市にうつられ、それいらい、両方の市場をお守りくださることになったのだそうです。
神度の御剣(森尻)
むかし、むかし、森尻に、まずしいけれども心のすなおな男の人が住んでいました。
ある夜のこと、神度の神様が夢枕にお立ちになって、
「わたしは、この宮居に飽いた。山手の清らかな地にうつり住みたいから、おまえは馬をつれてついてまいれ。」
とおっしゃいました。
男にとっては、馬は毎日のくらしになくてはならない大切なものでしたが、なにしろ、日ごろ自分が信仰している神様のおつげとあれば、ことわるわけにもまいりません。すぐ起き上がってうまやから馬をひき出し、神度の神様を馬の背におうつししました。そして、上市川を夢うつつのままにおしわたり、今の滑川市安田の坂にさしかかったところ、どうしたことか、馬は前あしを折って動こうとしません。
神度の神様はしかたなさそうに、
「こよいはかなわず、おしいことだが、もとの宮居にひきかえせよ。」
と男にすすめられました。
男は仰せのまま、痛がる馬をいたわりいたわり、ようやく我が家の近くまで来ました。
すると、神様は、
「たいへんごくろうかけたな。」
とていねいにお礼をおっしゃって、そのままお姿が見えなくなってしまいました。
このお社は文武天皇のみ代、大宝二年(七〇二)に佐伯越中守有若がお建てになったと言い伝えられていますが、別の説では、当時国司であった佐伯有頼卿が、お建てになったともいわれています。有若卿は有頼卿の父君にあたるお方です。
当社の全盛時代には、大きな宮殿を中心に、それにふぞくした小さな社、神社、そして、そこに仕えるたくさんの人たちと、それはそれは繁栄をきわめたといわれています。神社の領地も三千俵といわれるほど広い地面を持っていました。
しかし、上杉謙信が越中を攻めた時、ここもその兵火にあい、大切な神社の由来を書いた文書、宝物などは全部やけてなくなってしまいました。
そして、二十四坊も散りぢりになり、今は田んぼのところどころに大きな土台石がいくつか残っているだけで、わずかにむかしの宮殿、伽藍のあとをしのばせております。なお、今でも二十四坊のなごりとして、田の字に半人坊、十方坊、上専坊、法光坊、仁王堂などという呼び名が残っております。
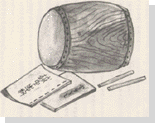 また、その時、一坊が若杉へひっこし、山王信仰の社家となって、そこに奉仕しました。その子孫が、現在の若杉日吉神社の宮司、二宮さんです。
また、その時、一坊が若杉へひっこし、山王信仰の社家となって、そこに奉仕しました。その子孫が、現在の若杉日吉神社の宮司、二宮さんです。
この山王信仰とは、白萩や南加積地区の山手にある日吉社と同じで、そのむかし、山手に住みついた人たちが、山の神気にふれ、山と生活をともにしてきたときに自然に生まれた信仰で、たいへん古いもののようです。平野部にある日吉社は、江戸時代までに山からおりてきて水田耕作に移った人たちが建てたのであろうと考えられています。
また、当時、仁王堂のあった所は、本社より約百メートルほど南の方で、今から数十年前にこのお堂の跡を開墾していたところ、一振りの剣を発掘しました。ある人が、これを家の宝物にしようと持ち帰ったところ、その夜から急に高い熱が出て、わけのわからない悪病にとりつかれました。いろいろ治療をほどこしてみますが少しも効き目が見えません。そこで、これはきっと、あの霊剣のたたりかもしれないと気がつき、おそろしくなって、すぐもとの所へ埋めました。するとふしぎや、今まで苦しんでいた病人は何かでぬぐいさったように病気がとれ、みるまにもとの元気な体になったということです。
さらにまた、この仁王堂の跡には永い年月、釣鐘が埋めてあって、毎年正月、元旦の朝には音色ゆかしくなりわたっていたとも伝えられています。
なお、先に書きました佐伯越中守が森尻に社殿を建てたことについては、次のように推理してみることができます。
延喜式内社は新川郡内に七社あります。神度神社はその中の四社と関係していることが注目されます。
それで、佐伯氏が越中に入ってまず居住したのは、下新川の布勢という所だといわれ、ここには布勢神社があります。今でも、魚津市斉木村に佐伯と称する子孫があって、藩政時代からずっと地方の名家でありました。
緒社に伝わる由来などをもとに考えますと、佐伯氏は布勢から森尻に来るあいだに、滑川の檪原神社を径て森尻に社殿を建て、さらに立山町の日中に社殿を建て、最後に立山を開き、雄山神社を創立したものと思われます。
のちに、京都山科の隨心院文書の中から、佐伯有若の署名が発見されました。それによりますと、先に書いた神度神社建立の年代とは少しくいちがいはありますが、有若は十世紀初めには、たしかに実在した人物であることが明らかになりました。
上市町でいちばん古い神社は、記録の上で、宮川村森尻にある神度神社だと言われています。
この神度神社は延喜式内社といって、たいへん位の高い神社であり、神度の剣がまつられてあることから、この名がつきました。
延喜式内社というのは、ずっとむかし、平安中期の醍醐天皇のころに編集された(九〇五─九二七)神名帳という書類にとうろくされている神社です。この神名帳にのっている神社は国内でも重要な神社で、特にていねいなあつかいを受けました。森尻の神度神社のほかに、ここらあたりでは、滑川市の檪原神社、立山町日中の日置神社、同じく立山町の雄山神社などが入っています。
神度神社の現在の神様は、豊受気神と神度神ですが、むかしの御神体は、国常立尊で仏像に似ていたといわれています。
あらたかな霊夢(森尻)
これも神度神社にまつわるお話です。
明和元年(一七六四)五月十二日のこと、宮の前に生えしげっている大きな杉の木かげで、近くに住む百姓たちがたばこをのみながら休んでおりました。
その日はものすごく強い南風で、ついうっかりと散らしたたばこ火は、たちまちすぐそばの杉の木の皮にもえ移りました。
おどろいた百姓たちは、ただおろおろするばかりで、どこを見ても水は一滴もありません。そのうち一人の百姓が気をきかし、そばにあった小便桶をみつけ、むちゅうでそれをひっかけて、ようやく火を消しとめました。ところが、その夜のことです。彦右エ門という人の夢の中に異人があらわれ、
「我は神度の神である。今日は里人が神木を汚したので、我の遊ぶ所がなくなった。よって、この地を去って早くとなり村へ移ろうと思う。村の豊右エ門の馬にのって行くからおまえがお供をしてくれ。」
と言って、姿が見えなくなってしまいました。
彦右エ門は夢の中でびっくり。深くおわびを申し上げ、お供していきました。二キロばかり歩き、前坂という所へ来た時、どうしたはずみか馬はひざを折って足を痛め、進むことができなくなってしまいました。
神様がまたおっしゃるには、
「今宵はここより帰る。」
そう言って馬を返されたところで彦右エ門は夢からさめました。
彦右エ門は、あまりのふしぎな夢にじっとしておれず、夜の明けるのを待って豊右エ門の家へかけつけました。そして、夢の一部しじゅうを話しました。すると、豊右エ門の家でも、ゆうべは飼い馬がうまやの中でどうしたことか、ひざを折って苦しみ出し、あまり痛そうだったので、馬医者を呼び、今見てもらっているさいちゅうだということでした。
彦右エ門は、ますますおどろき、こんなふしぎなこともあったものかと、晴れない思いのまま家に帰りました。
その夜、ふたたび彦右エ門の夢の中に神様があらわれ、
「心配するな。馬は四・五日もすれば痛みが治る。そうすればおまえが連れてかえるがよい。」
とおっしゃいます。
百姓たちが集まって話し合ってみますと、夢を見たのは彦右エ門だけではないことがわかりました。吉右エ門という者にも彦右エ門と同じく「お供をしてくれ」とおっしゃっておられますし、ほかの何人かにも夢の中に異人があらわれて、
「神のみこころに叶わず。後々、祟りがあろう。」
などとつげておられます。
村の人たちはたいへんおどろき、みんなで相談し、「これはきっと神木を汚したからにちがいない。」ということで、さっそくきれいな水で大杉を洗い清め、二宮若狭という神主さんを招き、お供え物をして、おごそかに祓いのごきとうをしてもらいました。
すると、その夜、みたび彦右エ門の夢の中に神様があらわれて、
「我、大杉にあそぶべし。」
とおっしゃり、それからはあのふしぎな夢を見る者がいなくなったということです。
まま子滝不動尊(釈泉寺)
むかし、むかしのことです。釈泉寺の村に、高さ五~六メートルの小さな滝がありました。その村に、後ぞえの母親が一人いました。夫がなくなったあと、くらしがとてもまずしくて、たいへんでした。七つか八つで、にくまれざかりの先妻の子どもと、かわいいわが子は、ことあるごとに、けんかばかりの日ぐらしをしていました。
ついにある日、思いあまって、まま子である先妻の子を、山へつれて行き、小さな滝の滝つぼめがけて、投げすててしまいました。
「おっ母、おっ母、助けてくれぇ。」
と、なきさけぶ声をあとに、心をおににして、ふり切って家へ帰りました。
ところが、毎夜毎夜、ゆめの中に不動明王様がおこった眼をつり上げてあらわれ、
「おまえは、なんという人非人(註1)じゃ。義理のある子を、なぜすてたのか。」
と、宝剣をふりかざしながら、
「おまえの命をどうしてくれよう。」
と、問いつめられるので、まま母は生きたここちもないありさまでした。
(ああ、これは正夢だ。)
と、急いでまま子をつれもどしに出かけました。なきつかれてなみだもかわき、すっかりやせほそって、ぐったりしている先妻の子のすがたを見て、思わずかけよってだきしめました。子どもは、一目見るなり、
「おっ母、おっ母。」
と、なきすがりました。
「ゆるしておくれ。ゆるしておくれ。わしほど悪い母親はいない。」
と、まま母は深く反省をしました。
不動明王様のおつげがなかったならば、三世に報いを受け(註2)なければならないところであった、とおそれおののく心をひきしめて、不動明王様をおがみました。
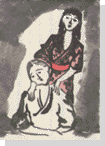 すると、きょうの不動明王様のお顔は、きのうまでと打って変わって、えみをたたえた、やさしいお顔に変わっていました。ないてわびをいう、まま母のざんげが、不動明王様に通じたのでしょう。
すると、きょうの不動明王様のお顔は、きのうまでと打って変わって、えみをたたえた、やさしいお顔に変わっていました。ないてわびをいう、まま母のざんげが、不動明王様に通じたのでしょう。
その後、子どもらの健やかな成長を楽しみに、母親はせっせと働いたかいがあり、まま子も、
「おっ母さん、おっ母さん。」
と、仕事を手伝い、親孝行をして、"孝子の家"と言われるまでになりました。
その滝は、だれが言うともなく、"まま子滝"とよばれるようになりました。
註1 人非人=人の道にはずれたことをする人。ひとでなし。
註2 三世に報いを受ける=子、孫、曽孫の三代にわたって、悪事のし返しを受けること。
与平お宮(折戸)
剱岳のふもとから流れ出る早月川というのは、たいへんなあばれ川で、むかしからたくさんの人たちを苦しめてきたものじゃ。この川の上流の早月谷に、折戸という村があってのう、この話は、そこに伝わっている話なんじゃ。
むかし、むかし。この村に与平という、えらく信心深い、心のやさしい若者がおったそうな。
そのころは買い物をするというても、遠い遠い上市村まで、一日がかりで行ってこんならんほどに不便なもんじゃった。だけど、この与平という人は親切なことに、自分が買い物に行く時は必ず、
「上市村まで行くけど、なんかいる物があったら買うてきてあげようか。」
と、村じゅう聞いて回っておったと。
あるとき、その日も山を下りて上市村まで買い物に出たんじゃが、たのまれた用事がたくさんあってのう。あっちこっちとかけ回っとるうちに、とうとう日がくれて暗うなってしもうたと。与平はよっぽど親類の家にとまっていこうかとも思うたけど、みんな待ちわびとるじゃろうと考えたら、それもできんし、山のような荷物をせおって、急いで帰ることにした。
歩き続けて、甘酒河原にさしかかると、
「与平、与平・・・・・・」
と、自分の名前をよばれたような気がした。暗がりをすかしてみたけれどだれもおらん。そら耳だったかと思うて行こうとすると、やっぱり、
「与平、与平・・・・・・」
と聞こえてくる。
声をたよりに近づいてみると、そこにはなんと百貫目(約三百七十五キログラム)ほどもある大きな石があって、たしかにそこから声が出とった。
「おまえに声をかけたのはわしじゃ。わしは水の神なのじゃが、おまえのしんせつにはいつも感心しておる。聞くところによると、早月川は大雨のたびに洪水を起こし、おまえたちはたいへん困っておるというではないか。わしが守ってやるから、せおって連れて行くがよい。」と、その水の神様は言わしゃった。
与平はえらいありがたいこととかしこまって、山のような荷物をせおってはおるけど、なんとしてもと決心してのう。さて、持ち上げてみるとびっくりするくらい軽くて、まるで、石がひとりでに動いとるようで、案じるまでもなく村に行き着くことができたそうな。
そこで与平は、村のみんなと話し合ってほこらを作り、その神様をまつったところが、それいらい洪水も少なくなって、村は大助かりじゃったと。
ところで、この神様はほこらの中でじっとしとるのがしょうに合わっしゃらんようで、気がつくと必ず、外に出とられるんじゃそうな。与平がせおった時にはあんなに軽かったのに、うそみたいにどぉんと重うなられて、村じゅう総出でふんばって、やっと中に入れましても、やっぱり外に出てしまわれるそうな。
今でもほこらの外で鎮座しとられるそうじゃけど、ほんとにふしぎな話じゃね。
村ではこれを「与平お宮」と名づけ、早月河原、折戸田んぼの守護神(註1)として、毎年五月七日に祭礼をおこなっているそうな。
註1 守護神=土地や人を守る神
大岩の不動尊(大岩)
むかし、むかし、行基というえらいお坊さんが、諸国をお回りになって北陸へおいでになった時のことじゃ。
越中の白岩というところにさしかかられた時、東の方のふもとに火の上がるのが見えたと。行基さまが、何事だろうとおどろいてそこへ行ってごらんになると、大きな滝がゴウゴウと音をたてて流れ落ちていたと。行基さまが祈りをこめて、大滝の下に杖をさし入れられると、大滝の上にすうっと、不動明王のお姿が現れたと。行基さまは、そのお姿にたいへん感げきなさって、このお不動様を岩に彫って、後々の世に伝えようと思われたそうな。そこで、あちこちとさがしたが、なかなか気にいった岩がみつからなんだと。
その時、白髪のおじいさんがひょっこり現れて、
「茗荷谷というところへ行くと、あなたがさがしている大きい岩がありますから、そこへ行ったらよいでしょう。」
そういってたちまちのうちに消えてしもうたと。
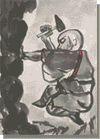 行基さまは、これはきっと神仏のお導きにちがいない、と思って、教えられたとおり山道をかきわけていったら、二十メートル四方もあろうかと思われる、大きい岩がみつかったと。行基さまは大喜びで、一心不乱に彫り続け、一夜のうちに『不動明王』を彫りあげられたそうな。
行基さまは、これはきっと神仏のお導きにちがいない、と思って、教えられたとおり山道をかきわけていったら、二十メートル四方もあろうかと思われる、大きい岩がみつかったと。行基さまは大喜びで、一心不乱に彫り続け、一夜のうちに『不動明王』を彫りあげられたそうな。
この不動明王は、上体を幅広くし、右腕の上の方も太く彫られ、いかにも下から仰ぐことを意識したようなつくりで、それが像に独特の迫力を与えています。また大きめの頭部にやはり大ぶりの眼鼻だちを明確に刻み、忿怒尊らしい威容を示しているのが特徴です。
右手に降魔の剣、左手に三昧の覇索を握り、脊に火炎を負い、波濤の上に座禅を組んだお姿です。
不動明王を中心にして、右に矜羯羅童子と阿弥陀如来像、左に制咤迦童子と行基菩薩と伝えられる僧形座像がすえられています。僧形二像は、表現の上からみて、平安朝か鎌倉時代(八、九百年前)に追刻されたものと思われます。
不動明王は、昭和四十九年六月八日、国の『重要文化財』に指定されました。
行基菩薩が、北陸をお回りになったのは、今から千三百年ほど前の聖武天皇のころの神亀二年(七二五年)七月のことと言われています。



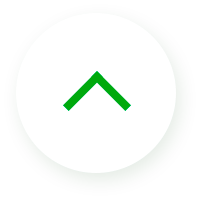


 つながる にぎわう ささえあう
つながる にぎわう ささえあう