本文
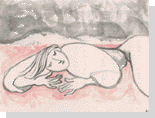
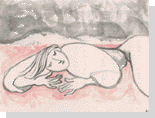
千石の豆山(千石)
今から七百年ほどむかしのことじゃそうな。
上市川のずっとおくに、小さな村があったと。
そして、その村一番の農家に、おみよという先妻の子と、おたえという後妻の子がおって、二人ともそれはきりょうよしだったそうな。
ただのう、後妻さんはどうしても自分の子どもがかわいいもんだから、おたえにいつもお祭りの時に着せるようないい着物を着せて「おたえ、おたえ」と何かにつけてかわいがっておった。
その反対に、先妻の子のおみよには、なんでも用事を言いつけてのう、みすぼらしい身なりばかりさせておったと。
でも、おみよはたいへんすなおな子だったものだから、「はい、はい」と不平ひとつ言わないで、おっ母さんの言うとおり毎日働いておったそうじゃ。
ある日、おっ母さんが二人の子どもをよんで、
「お前だっちゃ、これから村のかまてにある豆山に畑を作って豆を植えてこっしゃいや。」
と、それぞれ紙ぶくろに入った豆をわたしたと。
ところがのう、おたえにはふつうの豆だったのに、おみよにわたした豆は、火で煎った、食べればうまいけれど、植えても芽の出ん豆だったそうな。
二人はそれを知らないものだから、豆山へ行って畑を作り、豆をまいてのう、今も芽が出るか、はやも芽が出るかと、毎日畑へ行っては草を取ったり、水をやったりして、たいせつにしておったと。
ある日、豆山に行ってみると、おたえの畑から青い芽が出ておってのう、おたえはとんで家に帰り、
「おっ母さん、おっ母さん、おたえの畑からとうとう芽が出たいね。」
とおっ母さんにだきついて喜んだ。
けれど、おみよの方は、かわいそうに煎り豆とは知らず、芽が出ないのはきっと自分の丹精がたりないのだろうと、一人、畑に残っていっしょうけんめい草を取ったりしとったと。
おたえの豆は一日一日と目に見えて大きくなるのに、おみよの畑には、ざっ草ばかりで、いつまでたっても豆の芽が出てこなんだ。でも、おみよはあきらめもせず、朝は暗がりから畑にかよっておったと。
村の人たちは、どうしておみよの畑に豆の芽が出ないのかとふしぎがったり、ふびんがったりしておった。神様もこれを見ておられて、
「かわいそうに、母親のいじわるでおみよがえらいめにおうておるから、助けてやろうではないか。」
と、なかまの神様たちと相談されたそうな。
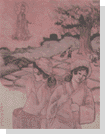 おみよが何も知らずに畑に行ってみると、どうじゃ。きのうまで芽の出ておらなんだ畑に豆の木ができ、どんどんのびておった。たまげたおみよは、村へとんで帰り、
おみよが何も知らずに畑に行ってみると、どうじゃ。きのうまで芽の出ておらなんだ畑に豆の木ができ、どんどんのびておった。たまげたおみよは、村へとんで帰り、
「おらの畑へ来てみられ、おばけの豆の木が出た。」
と、ふれまわったと。
さあ、村の者は何ごとだろうと、おみよの畑へ行ってみるとなんとまあ、一かかえもある豆の木が、大空に向かってのびておったと。
やがて秋になって、そのおおきな豆の木には、えだがまがるくらいに豆がなって、青空に金色にかがやいた。
そうして、いよいよ豆の木を切る日がやってきた。村じゅう総出で、
おみよの豆の木 エッサカ ホイ
おみよの豆の木 エッサカ ホイ
と、かけ声も勇ましく切りたおしたと。
いったいどれだけの豆があるだろうとはかってみたら千石(約十三トン)もあったと。
それから、この村を千石というようになったんだと。
やがて、豆の木はくりぬかれてたいこの胴となって、越前の永平寺に納められ、今も寺の宝としてたいせつにほぞんされているそうな。
また、豆の木を切ったとき、えだが上市川を流れ、ある坂に流れついたと。それを見つけた村人が、たくさん豆がついているのではかってみたら、五斗(約65キロ)もあったと。そこで、その坂を、五斗坂とよぶようになったんだと。
もう一本大きなえだが流れつき、そのえだから五百石(約六・五トン)の豆がとれたので、それからは、その土地を、五百石とよぶようになったそうな。
眼目の竜灯・山灯(眼目)
眼目の立山寺というお寺は、むかし、大徹和尚というえらいお坊さまが開かれたものじゃ。そのお寺ができあがるまでには大徹さまのご苦労を助けようと、立山権現さまやら山神、竜神さまなどが、いろいろとお力をそえてくだされたという話がある。じゃが、そのほかにもまだ、いくつかの話があってのうそのひとつを語ろうかいのう。
むかしから、七月十三日の夜になると、大徹和尚のお墓のある所へ、竜灯、山灯、といわれる二つの灯が、飛んできたもんじゃそうな。そして、お墓のそばの松の木の梢に、年に一度だけ、その二つの灯がついて、いっしょになってかかっておったと言い伝えられておる。
さて、その二つの灯についてじゃが、いったいどこから飛んでくるかというと、竜灯の方は、海からあらわれ、上市川尻にある高月村(今の滑川市)の浜を通り、魚躬村(滑川市西加積地区)加茂宮橋の橋の下から川伝いに上ったもんだそうな。とちゅう、石仏村(宮川地区)の宮林の杉の木にしばらくとどまったりして、上市川にそうてだんだんに上り、極楽寺の「えぼしが山」というところの松の木にかかって、山灯のやってくるのを待つんじゃと。
一方、山灯はどうかというと、これは、立山の称名が滝のあたりから出て、山越しに飛び、やがて、極楽寺の松の木まできて、そこで竜灯といっしょになると、二つそろうて、大徹さまの墓所の松の木まで飛んでいったもんじゃそうな。
竜灯、山灯、の二つの灯が待ち合わせた松の木は、今ではもうかれてしもうて、なんのしるしも残っておらんが、むかしの人は、それを「待合の松」と言うておったそうじゃ。
さて、この二つの灯のことを、もうちょっとくわしく言うてみると、山灯は色が大へんにこく、竜灯はいくぶんうすい色をしておったと。それが、今で言うたら夜の七時すぎから、二、三刻(一刻は二時間)の間、墓所の松の木のてっぺんにとどまっておったんだと。
やがて、この灯も帰る時刻になると、二つは松の梢を下りて、まるで地面にはいつくばるようにして、山灯は山のでこぼこした形にそいながら、こつこつと上り下りし、そのうちに、光がだんだん薄うなって、いつのまにやら見えんようになっていったと。竜灯の方は、すぐに前の川へ行き、川にそうて飛ぶようにしながら、海に帰ったそうな。
この竜灯、山灯は、毎年必ずやってくるかというと、そうでもなかったらしゅうて、風や雨のときはやってこず、まことに静かな闇の夜だけ、それもどうやらすると、一灯だけしかこないときもあったり、月日のずれもたまにはあったらしいのう。
この灯を見る者は、始めを見て終わりを見ず、また、終わりを見て始めを見ず、あるいは、中間を見て始終を見ず、というように、十人十色の見方があったそうじゃ。そうかと思うと、いっしょにおっても、見える者と見えん者とがあったりで、これはどうやら、信心のあるなしで、そのちがいがでてきたものじゃろう。
いずれにしても、大徹さまの徳を慕うむかしの人々が、大徹さまのなくなられたあと、いつまでも、信心の心をなくさんように、語り伝えてきたということであろうのう。
せみになった小坊主(大岩)
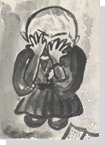 むかし、むかし、大岩の山ん中に、大きな大きなお寺があったと。六十もの坊舎が立ちならんでおって、修行する坊さまも、おまいりする人たちも、それはそれは多かったそうな。
むかし、むかし、大岩の山ん中に、大きな大きなお寺があったと。六十もの坊舎が立ちならんでおって、修行する坊さまも、おまいりする人たちも、それはそれは多かったそうな。
それがあるとき、戦があって、お寺はみんな焼けてしもうたそうな。負けた武士たちがにげるとき、お寺に火をつけていったのじゃ。
「小坊主や小坊主、お寺を建てなおすお金を集めるために、わしはこれから全国をまわってくる。ちゃんとるす番をしているんだぞ。さびしかったら、岩のお不動様におまいりして、心を強くもっているんじゃ。たのんだぞ。」
小坊主一人を残して、和尚さまは、旅に出てしもうたと。小坊主は目に涙をいっぱいためて、こっくんとうなずいた。
山の木の葉が散って、冬がやってきた。
雪やこんこ あられやこんこ
お寺のまえのさんしょの木に
一升五合たぁまれ
村の子どもたちは喜んだけど、小坊主はしょんぼり山門にたたずんで、和尚さまの帰ってくるのを待っておったそうな。
雪は、どんどん降り続いた。村人たちは窓をとざしてしまい、子どもたちは歌をやめたけど、和尚さまは帰ってこんかったと。雪はどんどんつもって、山門までうまってしもうた。小坊主は、火をたいたと。たいてもたいても寒かったと。どんどん、どんどん、火をたいた。そのうちに小坊主は、うとうととしてきたと。小坊主のまわりで、雪と火のこが、かわるがわるおどりくるった。
「和尚さまあ。まだですかいのう。さびしいよう。ああ、だんだん暗い、冷たいところへ落ちていく。火が消えるよう。こわいよう。和尚さまあ。早く、早く帰ってくださいよう。和尚さまあー。」
火は消え、雪はしんしんとふり続いて、小坊主のからだは、しだいに雪にうずまっていったそうな。
けれども、和尚さまは帰ってこんかった。
春が来て、あつい夏がやってきた。大岩山のこんもりしげった林の中に、今までだれも聞いたことのない蝉が鳴き始めたと。
ミーンミンミンミンミーン
ミーンミンミンミーン
その蝉の声はすきとおって、林の中をふるわせたそうな。
ミーンミンミンミンミーン
ミーンミンミンミーン
それは、小坊主がみんみん蝉になって、大岩山の林の中で、和尚さんを待って、鳴いているんだそうな。
若杉の逆さ杉(若杉)
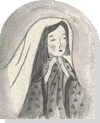 ずっとむかし、孝徳天皇のころ(六四五─六五四)、若狭の国(福井県)のあるりっぱなお家に、一人のお姫様がお生まれになりました。
ずっとむかし、孝徳天皇のころ(六四五─六五四)、若狭の国(福井県)のあるりっぱなお家に、一人のお姫様がお生まれになりました。
生まれながらにして白子だったので、大きくなってからは、自ら尼となられ諸国へ修行に出られました。みんなはこの尼となられたお姫様のことを、白いので白比丘尼と呼びました。また、比丘尼は龍神より不老長生の薬をもらって八百歳まで生きながらえたので、八百比丘尼とも呼ばれています。
比丘尼の伝説はいろいろありますが、越中にこられ、栃津の尖山の岩屋にも永く住んでおられて、栃津川や若狭川流域をたく鉢にまわられたといわれています。
ある日、比丘尼はこの若杉の地にこられました。ちょうど、お昼時だったので、大けやきの下に腰をおろして一休みされ、そばの杉の小枝を折って皮のついたまま箸がわりに昼食をおとりになりました。
食事がおわると比丘尼は、杉ばしを地面にさされ、
「この杉ばしは、やがて根がつくであろうが、それが樹になり、いつかは枯れる時が来る。その時こそこの比丘尼の死ぬ時である。」
と、ふしぎなことばを残して立ち去られました。
言われたとおり、まもなく杉ばしからは芽が出てきました。しかし、その杉ばしは地面にさかさまにさしてあったので、木はさかさまに大きくなっていきました。下よりも上が太く枝はみんな下をむいて伸びたのです。そこでだれ言うとなく「逆さ杉」と呼ぶようになりました。
今の若杉という地名はこの「若狭の八百比丘尼杉」から起きたものとも言い、また、一説には、逆杉を訛ったものだともいわれています。
この杉も、明治二十九年の台風に会い、樹は中途で折れ、中がくさって竹が生えてきました。村の人たちはこの杉をどうかして保存しようとトタン屋根を作り、保護につとめましたが、しまいには細い竹が何本も生え、皮だけの杉になり、ついには、まったく枯れてしまいました。昭和初期にはトタン屋根をかぶり、まだ一部のこっていたということです。
ある人が、そのそばに杉苗を植え、「さかさ杉のたましいよ、この木に移れ」とさかさ杉第二世をきたいしたそうですが、それはごく普通の杉に育ったということです。
比丘尼の伝説はほうぼうにあります。立山町の下田、あるいは下新川の村椿にもよく似た話があります。いずれも人魚の肉をたべて八百歳まで生きながらえたと書いてあること、また、福井県の小浜が関係してくることなど、同一人物と思われます。
五百石地方郷土史要によれば、「若狭の比丘尼の上下せし川を若狭川という」とあります。同女の縁起は現在、遠敷郡、空印寺にあるそうです。
ニカ福長者(広野)
むかし、むかし。広野の里に、一けんの貧しい家があってのう、そこに、年とった母親と、おさない娘とが住んでおったと。わずかばかりの田畑を耕す母親ひとりの働きでは、着物一まい買うゆとりもなく、米のごはんさえ、ろくに口にできんようなくらしぶりだった。
それでも、母親は、やさしい心をうしなわず、正直一途に働いた。おさない娘も、母親を見なろうて、子どもながらにいっしょうけんめい手伝いをし、母子よりそうて、その日その日をなんとか送っていたそうな。
ある秋の夕ぐれのことじゃ。
広い村里に、うす紫の夕もやがたちこめ、そろそろよいやみがせまってこようというころ、貧しい母子の住む、かたむいた家の戸口に、一人のお坊さまが立たれたと。
「どうか一晩、とめてもらえんじゃろうか。」
どこから歩いてこられたものやら、いっこうにわからなんだが、ほこりだらけになって、たいそうつかれておられるようすだった。
声をかけられて、母親はこまってしもうた。だいいち、お坊さまにごちそうしてあげるような食べ物は、こんな貧ぼうぐらしではあろうはずがない。母親は、心を鬼にして、
「見られたとおりのあばら家で、ろくなこともしてあげられんし、ほんとうに、申しわけないですが、どこか、ほかの家へ行ってくだされませ。」
と、ことわってしもうた。だが、そう言うてはみたものの、外はもう暗くなりかけておるし、これからまた、とぼとぼ歩かれるすがたを思うと、やっぱり、見るに見かねて、
「なんにもごっつぉしてあげられんねど、せめて、雨つゆをしのぐくらいなら。」
と、とうとう泊めてあげることにしてしもうたと。
お坊さまは、いったん、あきらめかけておられたふうであったが、母親のことばにたいそう喜ばれ、ちぎれかけておったわらじのひもを、ときはじめられた。
母親は、さて、なんとかして食べるものをよういせにやならん、何かはらのたしになるものはなかろうか、と、あれこれ思案をめぐらせておった。いくら考えても、ないものはないのだが、そのとき、ふと、庭のすみにこんもりともり上がっておるニカ(もみ)がらが目についたんじゃ。
「ひょっとして、あのニカがらの中に、わずかでも米つぶがあるかもしれん。」
母親は、とんでいって、そのもり上がったニカがらの中へ手をつっこんだ。わずかな田畑でも、年貢米はおさめにゃならん。自分らでたべる米も残さずに、持っていかれたあとのニカがらじゃ。あろうはずがないところに手を入れて、いっしんにかきまわしておると、それでも、ようよう、茶わん一ぱいほどの小米が拾いだされた。
母親は大いそぎで、その小米をうすでひいて粉にし、だんごにまるめてみそ汁にしたてた。ちくちくするもみがらの中から拾うた小米じゃ。おまけに、大あわてでこしらえたもんだから口の中までちくちくする、はじかい(ちくちくすること)だんご汁になってしもうた。それでも、腹をすかしておられたお坊さまは喜んで食べてくだされ、やがて、かたちばかりのふとんにくるまって、一夜を休まれたそうな。
さて、その次の朝も、母親は、お坊さまが目をさまされんうちにと、暗がりから起きて、ニカの中から小米を拾うておったと。するといつのまにやら起き出してきたお坊さまが、
「そのニカを、うすに入れてまわしてみなされ。」
と言われたそうな。
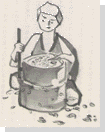 母親は、なんのことやらわけがわからなんだが、言われたとおりに、ニカをうすに入れてまわしてみた。すると、たまげたことに、ニカの中から大つぶの米がぽろぽろと出てきた。きつねにつままれたような思いのまま、庭にもり上がっておるニカがらをひいてみると、ぜんぶが、米つぶの入ったもみに変わってしもうておった。
母親は、なんのことやらわけがわからなんだが、言われたとおりに、ニカをうすに入れてまわしてみた。すると、たまげたことに、ニカの中から大つぶの米がぽろぽろと出てきた。きつねにつままれたような思いのまま、庭にもり上がっておるニカがらをひいてみると、ぜんぶが、米つぶの入ったもみに変わってしもうておった。
さあ、そのあとは、うすでひけば米とニカがらになり、ニカがらがまたもみになり、同じことのくり返しで米がたまるいっぽう、もう、そこらじゅうが、米で米でいっぱいになってしもうたと。
こしをぬかさんばかりにおどろいている母子を残して、お坊さまは、どこへともなく立ち去ってゆかれたそうな。さて、その後も、くり返しくり返し米が出てきて、あれほど貧しかった母子の家が、みるみるうちに、なやを建て、米ぐらを建てるほどになってしもうた。
近所かいわいのものはただおどろくばかり、なんで自分の家に坊さまがこられなんだやら、と、てんでんに、くやしがったりうらやましがったりしたけれども、こればかりはどうにもならん。やがてはこの家のことを、「ニカ福長者」とよぶようになったと。
そうして何年かの月日がたった。ニカ福長者はますます物持ちになり、丘の上には七つの米ぐらや、家財道具や財産を入れる土蔵を建て、御殿のような家に住み、ぜいたくいっぱいのくらしぶりになっておった。庭つづきの背戸の谷にはうぐいすを放し飼いにして、その鳴き声を楽しむなど、家運は全盛をきわめたそうな。
ところが、人の心というものは、いつか変わってゆくものとみえて、ありあまるくらしになれた母子は、むかしのびんぼうだったころのつつましさを、すっかり忘れてしもうた。心はおごりたかぶり、やさしさをなくし、となり近所の人がびんぼうしていても助けようともしなくなった。一升の米を借りにきても、ただびんぼうをあざ笑うばかりで、かしてやろうともせんようになっておったと。
さて、年ごろになった娘は、となり村の堀江城の領主さまのところへ嫁いでいったが、初めての里帰りの日は大へんなものものしさじゃった。
出世した娘をむかえるというわけで、母親ときたら、たくさんの財宝をつぎこんで、娘の通る道すじの、三つ屋野の村の入口の川に、黄金で作った橋をかけた。さらに、そこからわが家までの道には、もち米をついた大きなまるもちを飛び石がわりにしき並べ、その上をわたらせて娘を家にむかえ入れたそうな。
久しぶりにあった母親と娘は、一休みしたあと、今年もいっぱいになった米ぐらを見ようと、つれ立って米ぐらの戸をあけた。のぞきこんだ母子は、両手にいっぱいもみをすくってみたところ、あっとたまげてしもうた。なんと、米つぶで重いはずのもみが、中みのぬけた、かるいかるいニカがらになっておったと。
七つの米ぐらの、どこをあけてみても、かきまわす手にふれるもみはみんな、ただのはじかいニカがらに変わってしもうておったと。
ニカがらにまみれながら、母子は気がくるうほどに泣いたそうな。けれども、ぬけがらになってしもうたもみは、ふたたびもとへはもどらなんだ。
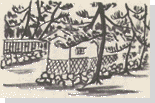 その家の背戸の丘を、それからはだれ言うとなく「ニカ塚」とよぶようになり、村人たちは、お金や物をむだ使いする者がいると、
その家の背戸の丘を、それからはだれ言うとなく「ニカ塚」とよぶようになり、村人たちは、お金や物をむだ使いする者がいると、
「いまに、ニカ福長者みたいになるぞ。」
といましめあうようになったということじゃ。
今でも、砂林開の村に、「糠塚」と「黄金橋」が残っておる。そして、春になると、むかしと変わらず、谷でうぐいすが、きれいな鳴き声をひびかせておるそうな。
穴谷の洞窟(黒川)
黒川地区の山あいに「穴谷」といわれる場所がある。そこにはほら穴があって、その中からわいて出る水は、どんな病気にでもよくきくといわれ、「霊水」とよばれて、大へんにもてはやされているのを知っておろうのう。今では、そのありがたい水をくもうと、遠くからやってくる人が列をなしているというぐあいじゃ。
穴谷は、黒川の村からさらにおくへ入った山の中で、むかしこのあたりは、まったくの原始林じゃった。
ずっとむかしは、「蛇の穴」とか「善光寺穴」とかいわれていたんだと。あるとき、この穴から、善光寺の焼印がおされた、柄杓やおわんが流れ出てきたので、この穴は信濃(長野県)の善光寺につながっている、というわけで「善光寺穴」といわれるようになったそうな。
実のところ、このほら穴は、むかしから、山伏などの修行の場として使われていたようで、むかし、弘法大師さまがこられたという言い伝えもあるんじゃと。
さてまた、今から百二十年ほど前、江戸時代の終わりごろ、美濃の国(今の岐阜県南部)本巣町から「白心」という行者がきた。初めのうちは、円念寺山(黒川村の上手の山)という手近な場所のほら穴で、座禅をくんでおったんだけれども、近くに護摩堂の村へ通ずる道があり、たびたび人が通るもんだから心が散ってしかたがない。そこで白心は、黒川の村の人たちに、
「どこかほかに、もっと落ちついて修行のできる、いい場所がないものだろうか。」
とたずねたと。そしたら、伊藤助右エ門という人や、そのほかの人たちが、
「穴谷になら、いいほら穴がありますぞ。」
というて教えたので、白心は、それからは穴谷に入り、二年と三か月の間そこで修行したということじゃ。
それから後も、ぼつぼつと、幾人かの修験者がほら穴をたずねて来たり、時には、夢のお告げ(註1)があったというて、穴の中から流れて出る水をくみにくる人などもあったそうな。
そのほかにも、はっきりしたところでは、明治三十年ごろ、能登(石川県)の荒木悟道という人が、この穴にこもって修行したもんだそうな。この人は、全国に布教してあるいた人だそうで、「鎌売り和尚」とも言われて、たくさんの信者をもっておった。
信者たちは、この人を生き仏さまとあがめ、その徳をたたえるために、黒川の村の入口に石碑を建てた。それには、大きい字で、「真解脱」と刻まれており、今も、道行く人たちの目をとらえるように、でん、と建っておる。
そのようなわけで、穴谷は行者の洞窟として、だんだん世の中に知られるようになっていったんじゃ。
ところで、近年になって、大正時代に月岡(富山市)の女行者が、また、昭和の初めには尾谷仙人といわれる人が、それぞれに修行をしている。昭和三十二年ごろには、佐渡が島や立山で修行したという広島県生まれの岡本弘真という女行者がやってきた。なんでも弘法大師さまが夢まくらにお立ちになって、この場所をお告げくださったそうな。
この女行者は、六年間もこの穴で修行し、昭和三十七年八月十七日に、五十九歳で亡くなったが、死にぎわに、
「穴谷にわき出る水は、とても霊験あらたかで、どのような難病にもよくきく。病に苦しんでいる多くの人たちにこれを飲ませてあげたい。私が死んだあとも、このことを長く伝えていってほしい。」
と言い残した。
今、穴谷の入口に立っておられる聖観音像の下に、この弘真行者の遺骨が納められているのだと。
さて、穴谷のふしぎな水の話は、県外へ行く売薬さんの口伝えなどで、ますます世間にひろまっていき、特に秋田県の方で有名になってしもうた。それというのも、ある売薬さんの口ききで、難病で足腰の立たない一人の娘さんが、秋田からつれてこられたんじゃ。
その娘さんは、穴谷のほら穴にこもって、毎日、いっしんに観音様をおがみながら霊水を飲み、湯治場でお湯につかることを続けておったら、いつのまにやら病気が治り、しっかり立って歩けるようになった。来るときは背負われてきたのに、帰りには、自分の足で歩いてかえったそうな。
こういう奇跡的な話があっちこっちに伝わって、穴谷のふしぎな水は、テレビの電波にまでのってしもうた。「穴谷の水には、今話題のゲルマニウムがふくまれているうえ、くんできた水は、いつまでたってもくさらない」と紹介され、県内の人たちはもちろん、はるか遠方から、観光バスを連ねてやってくる人びともおおぜいいて、今ではすっかり名物のようになってしもうたわい。
註1 夢のお告げ=夢の中で神様や仏様の知らせがあること。
種の谷右エ門(種)
むかし、白萩の種という所に、谷右エ門というまずしいお百姓さんがおったそうな。
ある年、谷右エ門は、おく山にあるごま山を開こん(註1)して、そこにじゃがいも、粟、稗などを植えたところ、たいそうよう育ってのう、たくさんの収穫があったと。そこで、谷右エ門はどんどん開こんして畑をひろげ、収穫をふやし、たちまちのうちに金持ちになったんじゃ。
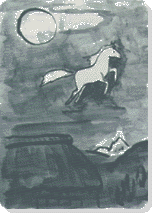 そのうえ、ある日、おく山から黄金のくつわ(註2)をはめた馬を、とらえてきたそうな。
そのうえ、ある日、おく山から黄金のくつわ(註2)をはめた馬を、とらえてきたそうな。
この馬は、お金の神様だったようで、おかげで八人の作男(註3)を使う、種ではならぶ者のない豪農(註4)になったと。
ちょうどそのころ、早月谷の下田という所にたいそうさかんな金山があったんじゃ。金山で働く人たちが食べる食料は、ふきんの村から集めても足らんもんで、残りは、谷右エ門から買うたそうな。そこで、飯米のなくなる夏場には、谷右エ門の家からたくさんの米が、金山へ運ばれていったと。
そのころはのう、「もみ」を大きなうすに入れてすって、げん米にしたもんじゃ。谷右エ門の家では、夏に岩あなの中で、暑さとたたかいながら「もみ」すりをせねばならんので、下男(註5)たちはたいそういやがったそうな。
下男たちは、
下田の金山 つぶれりゃよかろ
いやな夏ずり なけにゃいい
と、うたったということじゃ。
さて、谷右エ門はたびたび富山の城下まで用事でいくことがあったが、その時は必ずおく山でとらえた馬に乗って、金のくつわを"チャリン、チャリン"とひびかせながら通行したそうな。そのくつわの音は、一里(四キロメートル)も先から、よく聞こえたそうじゃ。
ある時、舟橋村の竹内という所のお百姓たちが、谷右エ門の馬が「若狭川」をとびこせるかこせないかで争いになった。わざわざ橋を落として、谷右エ門が通るのを待っておったと。やがて、谷右エ門が"チャリン、チャリン"とくつわの音をひびかせながら川岸まで来ると、橋が落ちている。そのまま引き返そうとすると、村人たちは、
「さては、川をとびこせないんだな。」
と口々にはやしたてた。
谷右エ門は、少しさがってから、くるりと向きをかえたかと思うと、勢いをつけて走り出し、なんなく大川をとびこえて、平然と富山をさして走っていったそうじゃ
じゃがのう、そんなに栄えた谷右エ門の家も、やがてかたむく時がやってきた。
谷右エ門の家では、むかしから家にいついた白蛇を守護神としてたいせつにしていたそうな。ところが、この家に来た嫁さんが、毎日のように集まるおおぜいの客のせわにつかれはて、なんとか客がこないようにする方法はないかと考えたすえ、ばんになると庭の四すみにくいを打ち、なわをはって客が入れないようにしたんだと。悪いことにそのくいの一本が地中にいた白蛇につきささってしもうた。
それいらい、お客もこなくなったが、同時に金のくつわをはめた馬も、月夜のばんに空を飛んですがたをかくしてしまったと。また、食料を運んでいた下田の金山も、このころにつぶれたそうな。
こんな不運が重なって、さしもの谷右エ門の家も没落してしまったそうじゃ。
註1 開こん=野や山をたがやして田や畑をつくること。
註2 くつわ=馬の口にかませ、手綱をつけて馬をあつかう用具。
註3 作男=やとわれて田や畑の仕事をする男。
註4 豪農=財産や勢力のある農家。
註5 下男=住みこみで雑役をする下働きの男。
不動さんと眼病(大岩)
百万石といわれた加賀藩に、名医といわれる人はたくさんいたが、眼医者にはあまりすぐれた医者はいなかったそうな。
三代目の前田の殿様は眼がお弱くて、八方手をつくして治療したけど治らなかったと。ところが、大岩のお不動さんにおまいりしたら不思議に治ったんだと。
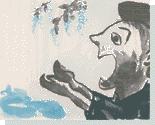 それよりもさらにむかしのことじゃ。お不動さんにはこんな話もある。越後のお百姓さんが眼の病にかかって盲目になったと。なんとしても見えるようになりたいと、息子に手をひかれて、二人で大岩の日石寺にこもったそうな。
それよりもさらにむかしのことじゃ。お不動さんにはこんな話もある。越後のお百姓さんが眼の病にかかって盲目になったと。なんとしても見えるようになりたいと、息子に手をひかれて、二人で大岩の日石寺にこもったそうな。
「どうか目が見えるようにしてください。どうか目が見えるようにしてください。」
と、滝にうたれたり、お百度まいりをして、いっしょうけんめいに祈願しておった。すると、二十一日の満願の日の夜、ゆめをみたそうな。ゆめの中にまっ白い髭のおじいさんがあらわれて、
「この山の大滝のわきに、藤の木が一本ある。その根もとから出る水で、目を洗ってみるがよい。」
といわれたと。とび起きて息子に話したら、
「ありゃあ、おらも今、同じゆめをみとった。」
と言ったと。
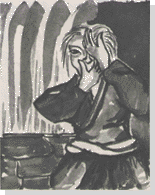 喜んだお百姓さんは夜明けを待って、まだ暗い道を息子に手をひかれて、つえをついて大滝めがけて歩いたと。ゆめの中の道を思い出しながら山の中を行くと、ゴォーッと大滝の流れ落ちる音がきこえてきた。山いものつるや、木の根っこにつまずいて、ころんだりすべったりしながら、息子は父親の手をひっぱって走ったと。
喜んだお百姓さんは夜明けを待って、まだ暗い道を息子に手をひかれて、つえをついて大滝めがけて歩いたと。ゆめの中の道を思い出しながら山の中を行くと、ゴォーッと大滝の流れ落ちる音がきこえてきた。山いものつるや、木の根っこにつまずいて、ころんだりすべったりしながら、息子は父親の手をひっぱって走ったと。
大滝のそばには、太い一本の藤の木が松にまきついて、天をつく勢いでのびておった。そして、藤の木の根もとには、ゆめにみたとおり、きれいな水が、さらさらと流れ出ておったそうな。
「あったあ。」
「あったぞっ。」
とさけんで、思わず水を両手ですくい、おしいただいて目を洗うと、これはふしぎ、たちまち両眼が開いたと。
帰りにはつえもいらなくなり、ひとりで歩いて日石寺まできたそうな。
それからこの水を、"藤の水"というんだと。
この水をお不動さんのところまで引いて、眼の病気でこまっているたくさんの人が、眼を洗い、お不動さんにおまいりして病気をなおすようになったんじゃ。
この清水をくみとるときには、お不動さまの御真言である
なうまくさんまんだ ばざだらん
せんだまかろしゃだ そばたや
うんたらたった かんまん
と唱えて、お不動さんの大慈悲をいただくんだと。
下田の金山(下田)
 むかし、むかし。下田というところに加賀藩が支配していた大きな金山があったそうな。ほってもほってもわくように金が出てつきることはなく、
むかし、むかし。下田というところに加賀藩が支配していた大きな金山があったそうな。ほってもほってもわくように金が出てつきることはなく、
「この金山はきっと佐渡の金山と続いているにちがいない。この世が続くかぎり、なくなる心配はまずあるまいて。」といわれておったそうな。
おかげで下田の村はたいそうなにぎわいで、なかでも坑夫たちのぜいたくな暮らしぶりは、目を見はるほどじゃった。札束をまきがわりにして酒のふろに入ったり、白米のおにぎりをぶっつけ合っておもしろがったりと、おそろしいほどのおごりたかぶりだったそうな。
それだけではない。
ある日のこと、酒によった坑夫たちは、折戸の神社まで出向き、こともあろうに御神体の首に縄をかけて早月川の河原にひきづりおろし、なぶり物にしたそうな。御神体は、かたうでをもぎ取られたむごいおすがたで河原にころがっておられたということじゃが、えらいばちあたりなこをしたものじゃ。
そのすぐ後におそろしいことが起こった。無尽蔵と思われた金山があっというまにくずれ落ち、ぱったりと金がとれなくなってしもうた。坑夫たちはばちがあたったと気づいたが、どうにもこうにも後のまつりじゃったと。
さしもの下田の村も死んだようにさびしい村にまってしもうたそうな。
ところがじゃ。このごろ、その金山に行って気をつけてさがしてみると、おどろいたことに、金が見つかることもあるそうな。だんだんとおごりたかぶってきている人間どもに、むかしの坑夫たちのような目に合わんようにと、神様が少しずつ金を出して、いましめておられるのかもしれんのう。
下経田の雨乞い石(下経田)
「あした天気になあれ。」と歌にもあるくらい、大人にとっても子供にとっても、あしたの天気は気がかりなものですね。その待ちのぞむ晴天もあまり長く続きすぎると、たまには雨のほしくなるときもあります。この石はそんなときに使われました。
下経田浄徳寺前にある石がそれです。
平らな安山岩で五輪塔が浮き彫りにしてあり、大日如来を示す梵字(註1)が書かれています。昭和三十四年に五輪浮彫供養碑として町の文化財に指定されました。
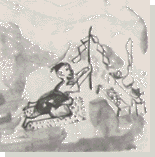 大きさは長さ一メートル、幅四十五センチで、雨がほしくなれば、ふだんは横になっているこの石をおこしてお祈りすれば雨がふるといわれています。それでだれ言うとなく、「雨ふり地ぞう」あるいは「雨乞い石」というようになりました。
大きさは長さ一メートル、幅四十五センチで、雨がほしくなれば、ふだんは横になっているこの石をおこしてお祈りすれば雨がふるといわれています。それでだれ言うとなく、「雨ふり地ぞう」あるいは「雨乞い石」というようになりました。
むかし、上市川がはんらんした時、上流から流れてきたものだといわれています。
むかしの上市川は今とは流れ方がちがい、山の合間から平地へ出ると、川は諸方へ、幾筋にも分かれていました。本流と思われるものには、極楽寺村から北島、稗田の南方の低い所を通り、法音寺・正印の間を通り、川原田で白岩川に注いでいたものだそうです。そしてこの川はたびたびはんらんしました。その時流れてきたものと思われます。
ところで、この石のある下経田は水には不足のない所ですが近くの若杉・稗田・北島はいつも水不足になやまされていました。そこで幾日も日照が続き雨がほしくなると、水不足の村の人たちがこの石をおこしにやってくるのです。しかし、地元では逆に、いつも水がたくさんあり、これ以上水がくると困るので、「寝ずの番」といって、夜ねないで見張りをする人をたてました。そして、こっそり石をおこしにやってきた者と大乱闘になったこともあるそうです。
今では多目的ダムもできて、どこもむかしのような深刻な水の心配はなくなりましたが、こうしてみると、この石は、農民と水との長い深刻な生活史を秘めた因縁のある供養碑ですね。
註1 梵字=古代インド語を書きしるす文字。
牛になった僧(森尻)
むかし、森尻権現につかえる多くの僧の中に、智明坊という人がありました。この智明坊さんは坊さんの身でありながら欲深くうぬぼれ強く、見栄っぱりの心の悪い人でした。
ある年、立山登山の道案内をしましょうということで、門徒の人たちをたくさん連れて立山に登りました。むかしのことですからバスなどはありません。重い荷物を背おって一歩一歩、歩いて行くのですから、さぞたいへんだったことでしょう。
 一同ようやく一の谷のくさりにつかまりながらはい上がり、やれやれと前を見ると、案内人であるはずの智明坊が、ふしぎや牛の姿に変身し、けさをかけたまま谷を越え、笹原の方へと迷い迷い行くではありませんか。
一同ようやく一の谷のくさりにつかまりながらはい上がり、やれやれと前を見ると、案内人であるはずの智明坊が、ふしぎや牛の姿に変身し、けさをかけたまま谷を越え、笹原の方へと迷い迷い行くではありませんか。
一同おおいにおどろき、口々に智明坊の名を呼んだり叫んだりしますが、智明坊ふり向きもせず、牛の声をのこしながら、とうとう見えなくなってしまいました。
 みんな、あまり急なできごとに何が何だかさっぱりわからず、おそるおそる参詣をすませてもう一度一の谷の上から原に向かって智明坊の名を呼んでみました。
みんな、あまり急なできごとに何が何だかさっぱりわからず、おそるおそる参詣をすませてもう一度一の谷の上から原に向かって智明坊の名を呼んでみました。
すると、一頭の牛がこちらの方に向かってかけてくるかに見えたのですが、それもそのまま遠吼えだけに終わってしまったということです。
その後の智明坊は、今までの自分をいっしんにざんげし、心を入れかえ、泰澄大師によって救われました。そして、光蔵坊という名まえの天狗に生まれ変わり、長く立山の天狗山に住んだと伝えられています。
しかし、越中史料によれば、この光蔵坊、また何の悪さをしたものか、剱岳の刀尾権現の怒りをかい、立山より追い出されたとのことです。
その時、爪を一つ落としました。その爪は今も社石として大切に保存されているということです。
古塚開き物語(正印)
正印の西の方に古い塚がありました。面積は八坪(約二十七平方メートル)あまりで、塚の上にはまわり二間(約三・六メートル)以上もある樹木が茂り、小さいながらに石の五輪塔などもありました。
むかしから、その塚の土中深くには、石造りの長持ちのようなものが埋められていて、多くの道具がしまわれていると言い伝えられていました。そして、塚の草木を折る者は恐しい祟りを受けると言われていましたから、人々は祟りをおそれて手入れする者もなく、あれるままになっていました。
後に耕地整理のとき、ここを開こんすることになりました。まず人々が寄り合い、お神酒を供えて、神様のお怒りを受けないようにおはらいをし、また、お経を上げて塚の霊をしずめました。その後、正印村の若者たちによって開こんされました。そのさい、あまり深くは掘りさぐらなかったからでしょうか。言い伝えられていた長持ちなどは見当たりませんでした。
今、そこは水田となっています。
開こんの時に、三十六体の石仏が出たという人もいます。
三枚滝の雨乞い(千石)
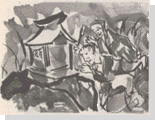 むかしは、何十日も日照りが続いて、田や畑に悪いえいきょうが出てくると、信州(今の長野県)の戸隠山から、九頭竜権現の水をもらってきて、上市川から用水への注ぎ口にまいたものだそうです。
むかしは、何十日も日照りが続いて、田や畑に悪いえいきょうが出てくると、信州(今の長野県)の戸隠山から、九頭竜権現の水をもらってきて、上市川から用水への注ぎ口にまいたものだそうです。
上市川の、ずっと上流にある三枚滝にも、雨の神をおこらせて雨をふらせるために、死んだ馬の首と、おかゆを投げ入れて水神の加護をいのったという言い伝えがあります。



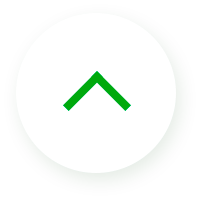


 つながる にぎわう ささえあう
つながる にぎわう ささえあう