本文
つぶら池(浅生)
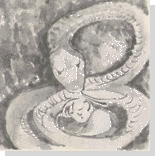 むかし、むかし。塔倉山のふもとの村に、仲のよい若夫婦がいてのう。二人は、毎日毎日野良仕事に精を出して、しあわせにくらしておったと。
むかし、むかし。塔倉山のふもとの村に、仲のよい若夫婦がいてのう。二人は、毎日毎日野良仕事に精を出して、しあわせにくらしておったと。
やがて、玉のような赤ちゃんが生まれてな。二人は大よろこびで、田や畑へ行く時も、山へぜんまいをとりに行く時も、赤ちゃんをつぶら(わらであんだかご)に入れて連れていくほどのかわいがりようだったそうな。
ある日、いつもいく池のふちに、赤ちゃんを入れたつぶらを置いて、少しはなれただんだん畑で働いておった。すると、そこへ、一人の見知らぬ女がやってきたと。そして、その女は、つぶらの中でねむっている赤ちゃんをみつけたがや。女は、赤ちゃんをじっとながめ、そのうちに、
この子がほしや この子がほしや
この子がほしや
と、うたったと。三べんうたうと、たちまち大蛇になって、つぶらもろとも、くるくる、くるくるとまき、池の底へ連れ去ってしもうた。
「何するが。坊や、坊や。坊やを返してっ。」
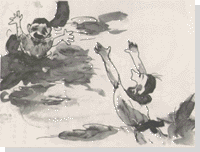 お母さんは、気ちがいのようになって、泣きさけびながら、池のまわりを走りまわったと。そうしたら、大蛇が出てきて、もう一度だけ見せてあげる、といって、つぶらごと高く池の上にさしあげ、またしずんでいってしまったと。
お母さんは、気ちがいのようになって、泣きさけびながら、池のまわりを走りまわったと。そうしたら、大蛇が出てきて、もう一度だけ見せてあげる、といって、つぶらごと高く池の上にさしあげ、またしずんでいってしまったと。
そのあとは、水の上に、五、六本のわらくずがうき上がってきただけで、いくら泣きさけんでも、池はしいんとしておったと。
それから、この池を"つぶら池"というようになったそうな。
後に、このわらの上に葦が生えしげって、それがうき島になってのう。小さなうき島は、雨がふる時は北東へ、晴れた日には南西へ、ただよい流れたそうな。付近の人は、このうき島の流れただよいかたによって、明日の天気をうらなっていたということじゃ。
これは、雨の日には、お母さんが、雨のふらない北東の山や畑へ働きに行き、晴れた日は南西のしめった所へ出かけていったからで、赤ちゃんのうき島が、お母さんをしたって流れるのであろうと、言い伝えられておるがのう。
浅生の釜池(浅生)
大岩のずっとおくに、塔倉山という山があるのを知っておろうのう。
むかし、むかし、この塔倉山に、ひとりのたいへん美しいお姫さまが、すんでおったそうな。いつもは、山のふもとの大きな岩の上にこしをおろして、炭焼き小屋から聞こえてくる笛の音を、じっと聞いては楽しそうにしておられたが、空が晴れて月のかがやくばんになると、なぜか、月をながめてはためいきをつき、さびしそうな顔をされるんだと。
炭焼き小屋には、たいへん気のやさしい若者がひとりいて、近くの木をきっては炭を焼いておったそうな。若者は、村一番といわれる笛上手で、いそがしい仕事のあい間に、月をながめては笛をふき、岩のところへ行っては、さびしいお姫さまの心をなぐさめておったと。
 ある月のきれいな夜のこと、お姫さまは、いつもよりもっとさびしそうにして、岩にこしをおろしておられたそうな。顔色は青ざめて、ときどき大きなためいきをつかれる。若者は、いつものように笛をふいてなぐさめるけど、姫はこの夜にかぎって、少しも喜ばれなんだと。
ある月のきれいな夜のこと、お姫さまは、いつもよりもっとさびしそうにして、岩にこしをおろしておられたそうな。顔色は青ざめて、ときどき大きなためいきをつかれる。若者は、いつものように笛をふいてなぐさめるけど、姫はこの夜にかぎって、少しも喜ばれなんだと。
「姫さま、どうしたのですか。今にも泣き出しそうな顔をして。わたしにわけを話してください。わたしにできることなら、なんでもしますから。」
若者がどう言っても、どうにもならないことだといって、お姫さまは、たださめざめと泣くばかりだったと。だんだん夜もふけてきたので、若者はしかたなく、
「姫さま、今夜はだいぶおそくなったので、これでおいとまさせていただきます。またあしたあいましょうね。」
と、帰ろうとしたら、お姫さまは、立とうともせずに、
「待って。悲しいけれど、たぶん今夜かぎりでお別れです。」
そういって、またまた泣かれたと。
「なんとまた、どうして急にそんなことをおっしゃるのです。姫さま、いつまでもここにいて、わたしの笛を聞いてください。」
そしたら、お姫さまは、泣きながらこんなうちあけ話をされたそうな。
「ほんとうのことを話しましょう。実はわたし、この山にむかしからすんでいる大蛇なのです。今年はちょうど天へ帰らなければならない年に当たっていて、あすの夜がいよいよ昇天の時なのです。それで、帰るころになるとこの山一帯に嵐が起こり、あたり一面どろの海になるはずです。あなたがこの炭焼き小屋にいると死んでしまいます。わたしはお友だちになったあなたを、見殺しにすることはできません。どうか、夜明けを待って、山をおりてください。やがてまた、美しい笛の音の聞ける日がくるのを待っています。けれども、この話はけっしてだれにも言わないでください。もし話すと、あなたの命はなくなります。」
それだけ言うと、お姫さまのすがたは、だんだん山の中へ消えていったんだと。
さて、若者は、この話を聞いてあまりのおそろしさに、こしもぬけんばかりにうろたえて村へにげ帰った。そして、思いなやんだあげく、村じゅうの人にこの話をしてしもうたんだと。村人たちもびっくりして、何かよい考えはなかろうかと、みんなで相談をしたそうな。
「むかしから、大蛇は鎌が大きらいだと聞いておる。今すぐ村じゅうの鎌を集めて、山へ登ろう。」
と長老がいったので、村じゅうの鎌を残らず集めて山に登り、お姫さまがいたという山をめがけて、ソレ、ソレ、ソレ、ソレ、と、力いっぱい投げつけた。
すると、今まで晴れていた空が黒雲につつまれ、ものすごい地ひびきをたてて山がくずれ、大雨になったと。どろ水は大きなうずをまき、あたりの大木は、バリバリッとうずの中にたおれこんでいったそうな。きもをつぶした村人はあわてふためき、命からがら村へにげ帰ったと。
次の朝、夕べのものすごかったことを思い出し、ゆめでなかったかと、村じゅう総出で山へ登ってみた。するとまあどうだろう。きのう、鎌を投げたあたりが、満々と水をたたえた一面の大きな池になっておったと。
恩人の若者のすがたはどこをさがしても見当たらなかったそうな。村人たちは、それからこの池を"鎌池"というようになったんだと。
今では「鎌」の代わりに「釜」の字を書いて"釜池"とよんでいるがのう。
滝橋の大蛇(釈泉寺)
 むかし、むかしのことでした。上市川の上流に、釈泉寺という村があります。その村のむこう岸に、"滝谷川"という、たいそう流れの急な川があって、上市川へ流れこんでいました。この川には、名前のとおり、いくつもの滝があって、今もそこに"滝橋"という橋がかかっています。
むかし、むかしのことでした。上市川の上流に、釈泉寺という村があります。その村のむこう岸に、"滝谷川"という、たいそう流れの急な川があって、上市川へ流れこんでいました。この川には、名前のとおり、いくつもの滝があって、今もそこに"滝橋"という橋がかかっています。
この橋の下には深いふちがあって、あたりには大きな木がたくさんしげっており、日中でも気味の悪いところでした。そのふちには大蛇が棲んでいて、はげしい風雨を起こしたり、夕方になると、美しい娘のすがたになって、近くの大きな桂の木の下に立って、そこを通る村人にいたずらをするので、村人たちも気味悪がって、夕方になるとそこを通らなくなりました。
この村に、たいへんかしこい、元気な若者がいました。そして、日ごろ村人たちが大蛇にからかわれているので、ひとつ、反対にからかってやろうと思いました。
ある夏の夕方、その桂の木の下の横を通ると、やっぱり娘のすがたになった大蛇が、立っていました。最近は、あまり人が通らないので、娘の方もたいへんたいくつそうでした。若者は、その娘のそばへ行き、
「娘さん、娘さん。だれでも、いろいろとすきなものと、きらいなものがありますが、あなたの大きらいなものは何ですか。」
と、たずねました。
すると、娘は、へんなことを聞くな、という顔をしながらも、
「わたしの一番きらいなものは、タバコのやにです。あれは、見るだけでも、身の毛がよだつくらいです。」
と、言いました。
若者は、これはうまいことを聞いたと、大喜びで村へ帰り、
「みなさん、みなさんがいつもいじめられていた大蛇を、こんどは、反対にいじめてやりたいと思います。大蛇のきらいなものは、タバコのやにだとわかりましたので、タバコのやにを、なるべくたくさんためておいてください。二、三日のうちに集めにまわりますから。」
と、村じゅうふれてまわりました。
さあ、村じゅう大さわぎです。今まで何回も、大蛇にいじめられているものですから、今こそかたきをとりたいと、タバコをすえないのに、むりをしてすう者などもあったりして、たくさんのやにが集まりました。
そこで、バケツに入った、たくさんのやにを持って、若者は村人たちに見送られながら、元気に滝橋へ向かいました。
桂の木の下に来ますと、いつものように美しい娘にばけた大蛇がいます。若者は、
「娘さん、娘さん。あなたの大すきなものを持ってきてあげましたよ。」
と言いながら、やにわに、バケツに入ったタバコのやにを、頭からざざっとかけ、
「わたしの一番きらいなものはお金で、ことに大判、小判は大きらいだ。」
と言って、いちもくさんに、にげ帰りました。
それから四、五日たったあるばん、若者が、家でむしろをおっていると、表のほうで、"チャリン、チャリン、ガチャ、ガチャ"という音がしたので、何ごとかととびだしてみると、なんとまあ、大判、小判が山のように積んであるではありませんか。
それから若者は、たいへん裕福になったということです。
大滝の大蛇(大岩)
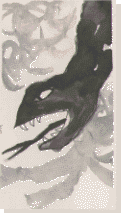 大岩川の上流、大滝のあたりに、胴まわりが二十センチメートルもあろうかと思われる、黒い大きい蛇がすんでいるそうな。この大滝からさらに五十メートルほど上流に、布を流したように流れ落ちる滝があって、これを流れ滝というておった。その滝の上の方に、これはまた大きい松の木が一本あってのう。
大岩川の上流、大滝のあたりに、胴まわりが二十センチメートルもあろうかと思われる、黒い大きい蛇がすんでいるそうな。この大滝からさらに五十メートルほど上流に、布を流したように流れ落ちる滝があって、これを流れ滝というておった。その滝の上の方に、これはまた大きい松の木が一本あってのう。
むかし、むかしのことじゃ。村の年寄りが、この松の木に大滝の大蛇がまきついて、赤いものすごく大きい口をあけて、目玉をどんぐり開いて、竜のように天をあおいでいるのを見たそうな。
この谷は煙草谷というて、日石寺所有の山なのじゃ。この蛇は、浅生の釜池と煙草谷との間を、いったりきたりしているが、人間にはぜったいに顔を見せず、胴だけ見せるのだそうな。
むかしから、この大蛇を見た人は、一生びんぼうしないといわれているわのう。



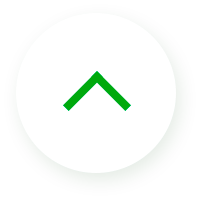


 つながる にぎわう ささえあう
つながる にぎわう ささえあう