本文
往生がま(西種)
いまはもう、あまり見ることができんようになったがのう。むかしは山の近くに住んでいる人たちの中には、田の仕事がひまになると、山へ行って炭を焼いて生活をしていた人たちがたくさんおってのう。白萩の西種という村にも、そんな家が何げんもあったもんじゃ。
そのうちの一けんに、たいそう兄弟仲のよい家があったんじゃが、ざんねんなことに、お父さんが病気で、あす死ぬかもわからないほどじゃった。でも兄弟はこれにひるまず、おたがいに助けあって、お父さんのかん病はもちろん、田んぼの仕事や炭焼きまでして家を守っておるもんで、近所の人たちはみんな孝行兄弟というて、自分たちの子どもの手本にしておったそうな。
この家の炭焼場は、家から二時間半ほど山に入った「うしろ谷」というところにあって、兄さんの方は、お父さんのかん病を弟にまかせ、自分はとまりこみでいっしょうけんめい炭焼きをしとったと。
ある日の夕方、兄さんが炭を焼いていると、
「あんちゃん、あんちゃん。」
という、弟のよぶ声が聞こえた。はて、今ごろどうしたんだろうと思っていると、弟が大きな息をはきながら、
「あんちゃん、たいへんだ。お父っちゃんが死にかかっとられる。早く帰ってくれ。あとはおれがやるから。」
と、言ったもんだから、かねてからかくごはしていたものの、びっくりした兄さんは、あとは弟にまかせて、大急ぎで山を下りて家に帰ったと。
ところが、お父さんは床から起きて夕飯を食べていなさるさいちゅうで、山に残っているはずの弟も、お父さんの横できゅうじをしているではないか。兄さんは、お父さんが元気だったので、ひと安心して今のできごとを話すと、
「それはたいへんだったのう。それはきっと山おくに住むムジナのしわざにちがいない。だが、よう帰ってきてくれたのう。」
と、お父さんは喜んでくれたが、兄さんは、ムジナにだまされたのが、くやしくてくやしくてたまらんかった。
それから半月ほどたったあるばん、兄さんがあい変わらず炭を焼いていると、月を背にして弟がいっしょうけんめい、
「あんちゃん、あんちゃん」
と、言いながらかけてくるではないか。兄さんは、はっと、いつかの事を思い出し、心の中では今にみておれと思いながら、表面ではたいへんおどろいたように、
「おう、おっちゃんか、今時分何ごとがあったがかい。」
と、歩みよって行くと、弟は息をはあはあさせながら、
「あんちゃん、たいへんだよ。お父っちゃんのようだいが急に悪うなって、親類のもんも来とられる。あんちゃんもすぐ山を下りてくれ。」
と、言うたと。
兄さんは、また前と同じ事を言って、案外ムジナもばかなもんだなと思いながら、
「えっ、そりゃたいへんだ。今、炭焼きがまを見てからすぐ山を下りるから、お前も手伝ってくれ。」
と、おどろいたそぶりで言ったと。
二人は、炭焼きがまの所に行くと、兄さんはやにわに、
「やい、ムジナっ。この前はよくもだましてくれたな。こんどはそうはいかないぞ。きょうはこの前のかたきをとってやるっ。」
と、言って、弟のすがたをしたムジナを炭焼きのかまの中に投げこみ、焼き殺してしまったと。
さあ、兄さんは、これでやっとかたきをとることができたと、あくる朝、山を下りて行くと、とちゅうで会った村の人たちが、
「このたびは、たいへんお気のどくなことで・・・・・・。さびしくなられたでしょう。」
と、おくやみを言うではないか。
はて、おかしいなあと思いながら家に着くと、家には黒いまくがつってあって、お父さんがほんとうに死んでおられた。そして、弟のすがたも見えんかった。
では、昨夜のできごとは・・・・・・・・・。
兄さんは、ほんとうの弟をムジナとまちがえて、殺してしまったのじゃった。
一度に父と弟をなくした兄さんは、それから家を出て、仏門に入り、二人のめいふくをいのったということじゃ。
稗田の鬼(稗田)
むかし、むかし。稗田の黒川原というところに、一けんの鍛冶屋がありました。たいへんな金持ちで、鍛冶屋敷とよばれる大きな屋敷をかまえ、広い土地を持って、なに不自由のないくらしをしておりました。
しかし、この鍛冶屋にも一つのなやみがありました。それは、家の後をついでくれる男の子がいなく、女の子が一人いるだけだったということです。
そこで、主人は早く娘に婿をとりたいと思い、つぎのような立てふだを村の辻々に立てました。
「このたび、わたしの娘に婿をむかえたいと思う。ただし、婿になる者にはじょうけんがある。そのじょうけんとは、夕方から明け方の一番どりが鳴く間に、千本のやりを鍛えた(註1)者にかぎる。」
さあ、村じゅうはもとより、近郷(註2)近在では、よるとさわるとこの話でもちきりになりました。金持ちでおまけに娘が美人というのですから、希望者がたくさん集まりました。
その中に、前から娘におもいをよせていた鬼が、今こそと若い男にばけて婿えらびに志願していました。
やがて、志願した若者たちが一堂に集められ、主人から、
「このたび、わたしの娘に婿をとるために希望者を募ったところ、たくさんの若い衆が集まってくれ、たいへんうれしく思っている。だが、立てふだにも書いておいたように、わしの家は鍛冶屋であるので、一夜のうちに千本のやりを鍛えるくらいの者でなくては、わしの娘の婿にはできない。これから一人ずつ仕事場に入って、やりを鍛えてみせてほしい。」
と、言いわたされました。
そのばんから一人ずつ仕事場に入れられ、やりづくりを競うことになりました。
しかし、ひとばんに千本のやりを作るのですから、なかなか人間わざで、できるものではありません。やる者やる者みな失敗して、いよいよ若者にばけた鬼の番になりました。
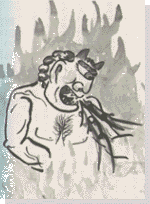 そのばんは、いつもなら聞こえてくるふいご(註3)の音も、金床を打つ音も、ぜんぜん聞こえてきません。主人はふしぎに思い、そっとのぞいて見ると、なんと、若者は鬼のすがたになって、口から火を吐きながら鉄のぼうをのばし、みるみるうちにやりに作り上げていくではありませんか。主人は、
そのばんは、いつもなら聞こえてくるふいご(註3)の音も、金床を打つ音も、ぜんぜん聞こえてきません。主人はふしぎに思い、そっとのぞいて見ると、なんと、若者は鬼のすがたになって、口から火を吐きながら鉄のぼうをのばし、みるみるうちにやりに作り上げていくではありませんか。主人は、
「これはたいへんなことになった。いくらなんでも鬼をだいじな娘の婿にすることはできない。なんとかうまい方法がないものだろうか・・・・・・・・・。」
と、いっしょうけんめい思案しました。
仕事場では鬼がどんどんやりを仕上げて山と積んでいきますので、主人は気が気ではありません。夜もだんだんしらみはじめました。
ふと、主人はうまい方法を考えつきました。主人は大急ぎで台所に行き、やかんで湯をわかし、鶏小屋に持っていきました。そして、竹で作った止まり木のつつの中に湯を流しこみました。
止まり木でねむっていた鶏は、だんだん足もとがあたたかくなってきたものだから、これはきっと太陽がのぼってきたものと思い、ね過ごしてしまってはたいへんとばかり、あわてて、
「コケコッコー。」
と、大声で鳴きだしました。
千本にあと一本というところで、鶏が鳴きだしたのです。
「ちぇっ、残念・・・・・・。だが、まてよ。まだ暗いのに一番どりが鳴くということは、きっと自分の素性(註4)がばれてしまったにちがいない。」
鬼は自分で作ったたくさんのやりをかかえるや、屋根をけやぶって空高くにげ去ったということです。
註1 鍛える=ここでは金属を熱し、たたいて強くすること。
註2 近郷=近くの村。
註3 ふいご=鍛冶屋が火をおこすのに用いるかんたんな風を送る道具。
註4 素性=血統、家柄、育ち。ここでは、自分が鬼であること。
三本杉と天狗(神明町)
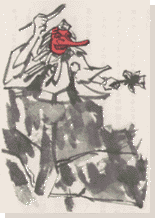 上市高等学校の横に、日露戦争の勝利を記念した神武天皇の銅像や、戦没者の忠魂碑などのある、三杉公園があります。その三杉公園のまん中に、今では、なくなってしまいましたが、大きな三本の杉の木がありました。なんともりっぱな杉の木で、おとなが四人でようやくかかえられるほどの太いみきが、空高くそびえていました。
上市高等学校の横に、日露戦争の勝利を記念した神武天皇の銅像や、戦没者の忠魂碑などのある、三杉公園があります。その三杉公園のまん中に、今では、なくなってしまいましたが、大きな三本の杉の木がありました。なんともりっぱな杉の木で、おとなが四人でようやくかかえられるほどの太いみきが、空高くそびえていました。
「じまんするなよ 三本杉ゃ近い
鼻の高い人 見てござる」
と、むかしから子どものころに、よく言いはやしたもので、三本杉には天狗が住んでいるといわれていました。
よく、子どものころ親に、いたずらしたときなど、
「三本杉の天狗が連れに来るぞ」
と、言われて、ほんとうにおそろしかったものです。
むかし、あるきこりが、三本杉の大きな枝を一本切ってきて、家で仕事をしていると、なんとその夜、その家から火が出て、みるみるうちに上市じゅうが火の海となり、あっというまに灰になってしまいました。その時から、この三本杉を、神木(神様の木)としておまつりすることになったと言い伝えられています。
この杉は、いつごろからあったかよくわかりませんが、もと、眼目の杉並木の一部であったと言われています。四百年ほど前、上杉謙信が稲村城を攻めたとき、立山寺の伽藍とともに杉並木も焼かれてしまい、この三本だけが残ったのだそうです。
また、眼目の参道の入口が今の森尻だったので、森の尻の意味で森尻村と名づけられました。もちろん、そのころの上市川は、森尻の方へは流れていませんでした。
いたずらぎつね(森尻)
今から七十年ほど前(大正の初めごろ)は、まだ電車もなく、物を運ぶにはせいぜい荷車を使っていました。
滑川あたりの魚屋さんも、浜から天秤棒をかついで、前後のかごにいっぱい魚を入れて上市まで売りに来ましたし、また上市からは、山の青草(うど、よしな、ふきなど)を荷車につんで、滑川方面へ売りに行っていたものです。
そのころ、青ものの商売に朝早くから精だしている一人のおばあさんがいました。このおばあさんは、若いころからこの商売を続けていましたから、いろんな目にもあってきましたし、たいがいのことにはおどろかなくなっていました。でも、この時ばかりはおそろしかったと、話してくれました。
当時は、上市の火葬場ふきんは人家がなく、お寺だけのさびしい所でした。
ある時、滑川のお祭りで、そのおばあさんにたくさんの注もんがありました。おばあさんは、なるべく朝早いうちに滑川に着きたくて、荷車に青草を山と積んで、夜の十二時すぎにはもう火葬場の前まで、おじいさんに送ってもらってやってきました。
おじいさんと別れて五分もたったでしょうか。荷車を、おしたり引っぱったりするものがいます。おじいさんがまだおしてくれていたのかとふり向くと、ふうっとひと風ふいて、ちょうちんの明かりが消えてしまいました。
「おじいさん」
と声をかけても、返事がありません。おかしいなと思い、少しこわくなったので、お念仏をいっしんにとなえました。
 森尻をすぎたあたりで、また荷車をおしたり引っぱったり。そして、こんどは、風もないのに明かりがぱっと消えました。
森尻をすぎたあたりで、また荷車をおしたり引っぱったり。そして、こんどは、風もないのに明かりがぱっと消えました。
おばあさんは全身耳にしますが、なんの物音も気配も感じません。こんどは、荷車の音に負けないほどの声でお念仏をとなえ、力をふりしぼって、しだいに足ばやに荷車を引きました。ついに大永田の村の中にある豆腐屋さんにかけこみました。
ようやく息をととのえ、早起きの豆腐屋の老夫婦にこのことを話しますと、
「ここらはきつねがいたずらするがいね。おそろしかったろいね。」
老夫婦も念仏をとなえながら豆腐作りに精を出しました。
東の空がしらみ始めるころ、老夫婦に送られて、おばあさんは滑川へ急いだということです。
かっぱのガンザブロウ(蓬沢)
蓬沢の村のはずれを流れている下田用水は、昔から川下の下田村の田んぼをうるおしておりました。その用水の中ほどにけわしいがけがあって、絶壁の下をえぐるように、早月川の水がよどんでふちになっている所があります。その場所は、「ガンザブロウ」と呼ばれています。
むかし、そこに、かっぱのすがたをしたかいぶつがすんでおって、子どもをさらうやら、大人をだますやら、悪さのかぎりをつくして村人を困らせておりました。人々はそれを、「かっぱのガンザブロウ」と呼び、たいそうおそれておりました。
ある日のこと、村の笹林久次郎という人が、そのふちで馬の足を洗っていると、そこへガンザブロウがあらわれて、馬の足にかみつきました。おこった久次郎はかくとうのすえ、ガンザブロウのかた足を引きぬいて、家に持って帰りました。
そのばん、久次郎がねていると、まくらもとにガンザブロウがあらわれて言うことには、
「足を返してほしいんじゃ。返してくれたらおまえに、どんなけがにもよくきく薬の作り方を教えてやろう。わしはうそは言わん。たのむから返してくれ。」
そう言ったと思うと消えてしまいました。
あくる日、久次郎は半信半疑のまま、ガンザブロウの足をかかえてそのふちに下りて行きますと、ガンザブロウは待ちかねておりました。足を受け取ると、やくそくどおり「あいす」という薬の作り方を教えてくれました。
その後、ガンザブロウの悪さもぴたりとやんだそうです。久次郎は聞いたとおりに薬を作り、ためしてみたところが、びっくりするほどよくきいたそうです。そして、いつまでもその薬を作り続けたので、村人たちはたいそう助かったということです。
きつねの嫁入り(北島)
昭和の初めごろ、町から山の学校へかよっていた、ある女先生が、学校の帰り道、実際に出あったというお話です。
そのころの山道はほとんどがせまくてがたがたで、坂道はけわしく、たいへんさびしいものでした。ことに、昔、大蛇が出たと言われる滝橋あたりは、ぞっとするほどさびしい所でした。
ある秋の土曜日、一日の仕事を終えたその女先生は、四時ごろ学校を出ました。極楽寺までいっしょにきた友とも別れ、一人、わが家へと急ぎました。極楽寺から北島までの間には家はまったくありません。
上市川のせせらぎを聞きながら、暮れてゆくさびしい秋の道を歩き、ようやく北島の入口に近づいた時です。ふと右のかなたを見ると、川向こうの斉の神あたりに、ちょうちんの明かりが、消えたりついたりして長い行列を作っています。
「今ごろ、あれはなんの明かりだろう。眼目の立山寺へ修行に来たお坊さんたちかな。」
と思い、急ぎ足で北島口のお地蔵さんの前を過ぎると、ちょうちんの明かりが川越えにゆれてしだいにこちらに近づいてくるのです。足は自然に速くなりました。
その時、ちょうど山へ帰る馬車ひきのおじさんに出会いました。
「ちょっと、馬車ひきのおじさん、あれ見られ、あの明かりこっちへたくさんくるけど、何があったんけ。」
言われて気づいた馬車ひきのおじさんは、
「ありゃね、きつねの嫁入りだぞいね。いやだね。気いつけてだまされんようにいかれませ。」
馬車ひきのおじさんは、鼻歌を歌いながら山の家へと向かいましたが、女先生は腰をぬかさんばかりの気味悪さにおそわれて、走り続けて家へ帰りました。たどりついた時は、あせびっしょりだったということです。
きつねお宮(法音寺)
今から六十年ほど前(大正の終わりごろ)のお話です。
上市の町もまだむかしのことですから、家の数が少なく、町でも、家がぽつんぽつんと離れて建っていました。いちめん田んぼ続きで、馬の首につけた鈴がチリンチリンと耳を楽しませてくれたころのことです。村と村との間にはほとんど家がなく、夜は人通りもありませんでした。
法音寺のお宮様(村上神社)も田んぼの中にぽつんとありました。こんもりとした森に包まれて、お祭りのとき以外は人の出入りはあまりありませんでした。このお宮様を昔から「きつねお宮」と呼んでいました。
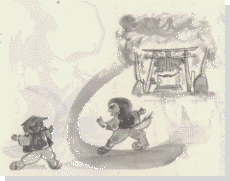 ある日の夕ぐれ、一人のお百姓さんが親類へ行って帰るとちゅう、このお宮様のあたりへ来た時、手ぬぐいでほほかむりしたおじいさんがあらわれたかと思うと、
ある日の夕ぐれ、一人のお百姓さんが親類へ行って帰るとちゅう、このお宮様のあたりへ来た時、手ぬぐいでほほかむりしたおじいさんがあらわれたかと思うと、
「ついてゆくゆくコンコン。」
といいながら、宮の境内にすうっとすがたを消しました。
お百姓さんはびっくりして、あたりをみまわしましたがだれもいません。目がくらんで、どこがどこだかまったくわからなくなり、田んぼに落ちてどろんこになってはいまわりながら、手さぐりでようやくあぜ道を見つけて歩いていくと、こんどは森の方からコンコン、コンコンときつねの声がします。おそろしさのあまり、にげるようにして家に帰り、家族の者にそのことを話し、その夜はそのままねてしまいました。
つぎの朝、近所のおじいさんに夕べのできごとを話しました。
すると、
「わしも以前、そんなめにあいましたちゃ。夕方には外に出られんちゃ。おそろっしゃな。」
と、おじいさんは、そのときの恐しさを思い出したかのように話してくれました。それからは、人々はますます「きつねお宮」へ行かなくなり、たいへん淋しいところでした。今では、近くに工場や小学校、民家などがたくさん建ちならび、人通りも多くなって、きつねの話しも聞かなくなりました。



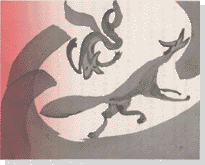
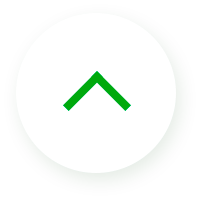


 つながる にぎわう ささえあう
つながる にぎわう ささえあう