本文
伊折の源助(伊折)
むかし、むかし。伊折村に源助というきこりの頭がおってのう。この男はどきょうがあって力持ちで、そのうえ走るのも速かったもんだから、いつも山の中に入り、けものを素手で打ち殺しておった。
ある日のこと、源助は二、三人のなかまと出会い、いっしょに山に入ってけものをとらえて食べようという話になって、みんなで黒部峡谷へ出かけた。たがいに負けてなるものかときょうそうして狩りをしたところが、一日でなんとえものを七十ぴきもとらえてしまった。これがみんな、てっぽうとか刃物など使わず、素手でやったという、たいした剛の者ばかりじゃった。
ある時源助は、同じ村の作兵衛というきこりといっしょに、黒部峡谷の井戸菊谷という所に入って、いっしょうけんめいに働いておった。日もくれかかったころ、急に風雲が起こり、山々が地震のように鳴り動いた。いっしょにいたきこりたちは大あわてで次の谷の小屋までにげおおせたけれど、作兵衛だけは、もうちょっとのところで、今までに見たこともないおそろしいかいぶつに捕えられてしまって、空に連れ去られそうになった。
源助は、作兵衛がにげおくれたと知るや大急ぎで引き返した。今にも宙へまい上がりそうな作兵衛を見つけると、むちゅうで飛びつき、引き下ろそうとした。かいぶつも負けじとえり首をくわえてはなそうとしない。上と下とで引っぱり合いとなり、作兵衛はますますぐったりと死んだようになって、口から赤い血しおを吐いた。
源助はまっかになっておこり、山々にひびきわたる声で、
「やいちくしょうめ、早く作兵衛をはなせ。そうせんと、かたっぱしからおまえらのなかまをつかみ殺してやるぞ。すぐに作兵衛をおれにわたして、どこへでも消えてしまえ。」
とさけんだが、かいぶつはいっこうにはなさない。
源助はますます大声をはり上げて、
「おのれ、伊折村の源助を知らんで、この山に住めると思っとるのか。作兵衛にもしものことがあったら、おまえたちのことはぜったいに許さん。毎日山に入っておまえらを粉々に打ちくだいてくれるぞ。わかったか。」
とわめいたが、どうにもならんかった。
えらい長い時間がすぎて、とっぷりと日が暮れてしもうた。作兵衛の口から流れ出る血しおで源助は体じゅうまっかにそまってしもうたけど、かたときもゆだんなくしっかりとつかまえておった。
朝の四時ごろになって、さしものかいぶつもあきらめてしもうたか、作兵衛をはなして消えてしもうた。作兵衛は源助のせなかにかぶさるように落ちてきた。
「作兵衛、作兵衛。」
と名をよんでいっしんにかいほうしておると、東の空がだんだんと白んできて、仲間のきこりたちもまたもどってきた。薬を飲ませるやら、水をやるやらしたところ、やっと作兵衛は気がついた。山小屋に運んで静かにねかせていると、数日で元気になった。源助のおかげで作兵衛は一命をとりとめることができ、ほんとうによかったことじゃ。
こんなことがあってからも源助は、一日も休まずに山に入って木を切り続けた。さすがのかいぶつも恐れをなしたか、その後は何も起こらんかった。ただ源助は以前と違って、しきりと考え深そうな顔つきをしておった。
「作兵衛をひどい目に合わせたやつは、狒狒か、もうじゅうか。大きさや色からすると熊でもないようだし、風雲を呼ぶという、とらやひょうの仲間かもしれん。じっさいのところ、さっぱりわからんなあ。」
きこりたちは顔を合わせるたんびに、この話でもちきりじゃった。
何日かたって、源助はきこりたちを集めた。
「わしはこの数日考えておった。作兵衛をひどい目に合わせたのは天狗でも山の神でもない。悪いもののけのしわざにちがいあるまい。中でもいちばんおそろしいのはうわばみじゃから、これから身を守るには、いつも山刀をこしにつけておくことじゃ。これを身につけておると、うわばみにのみ込まれる心配はないとむかしから言われておる。それを忘れて、近ごろちょっとゆだんがあったようだ。」
そう言って、源助はきこりたちにこんな思い出話をしはじめた。
むかし、駄兵衛という者がおったが、山刀はじゃまだといって、言いつけも守らんとはずして山仕事をするようになってしもうた。一月ほどは何事も起こらんかったが、ある日のこと、しかもまっぴるま、きこりたちはなんともいえずへんな声を聞きつけた。ふと見ると、駄兵衛が異様な声を出して向こう岸をにげ回っておる。追われ追われて必死に木に登り始めた。追いかけ回し、とるもののすがたはまったく見えんかったが、うわばみにちがいない。なまぐさい風を起こし、きりのような物をふき散らすので、なんともがまんのできん気持ちの悪いにおいの大風がふきあれておった。
狼なんかだったらなんとかにげのびたかもしれんが、うわばみというのは、もともと木をわがものにしておるやつだから、ひとたまりもない。駄兵衛は何か大声でさけびながら、こずえからまっさかさまに落ちたと見えたとたんに、ひとのみにされたか、音も立てずに消えてしもうた。きりの中で、うわばみの気配はするがすがたは見えず、三尺余り(約一メートル)の白い光があちこち飛んどるだけじゃった。
「うわばみはあやしい妖気(註1)を持っとるそうだから、その妖気で相手をやっつけてしまい、全身を見せることはないのかもしれん。作兵衛の災難の後、わしはこの話を思い出した。そんなわけじゃから、かたときも山刀を身からはなさんように。」
これを聞いたきこりたちは、それいらい山刀の手入れをおこたらず、心して身につけるようになったそうじゃ。
註1 妖気=何か起こりそうな気味悪いふんい気。
法音寺のせき止め(法音寺)
 むかし、むかし、こんなことがありました。何日も降り続く長雨に、上市川は、ついにはんらんしてしまったのです。濁流は土堤をのりこえ、法音寺方面めざしてすさまじい勢いで流れこんできました。
むかし、むかし、こんなことがありました。何日も降り続く長雨に、上市川は、ついにはんらんしてしまったのです。濁流は土堤をのりこえ、法音寺方面めざしてすさまじい勢いで流れこんできました。
その時、人々がさわぐ中を、六尺(約二メートル)板を何枚もひっさげて、上手に走る一人の老人がいました。法音寺一帯の大地主(註1)九郎三郎です。
老人は勇敢にも濁流の中に飛びこみました。水は胸のあたりまできて、危うく押し流されそうになりました。よろける足をふんばりふんばり、一枚、二枚と、六尺板を流れにあてていきました。
老人のこの必死の努力によって、さすがのすさまじい流れもついにせき止められました。村の若者たちもかけつけて手伝いました。おかげで法音寺一帯は大事に至らずにすんだのです。
このせき止めた所は今の法音寺、村上神社のやや南、木のある所あたりだといわれています。小字三郎田といわれる場所ですが、付近の田には砂利が多いけれども、ここだけはないといわれています。
このせき止めによって川は左右にわかれ、法音寺の一部が川向になり、これを「向かい法音寺」といいました。
上法音寺、法音寺、横法音寺、大坪法音寺、それに向かい法音寺を合わせ、五法音寺といいます。
註1 大地主=土地をたくさん持っている人。




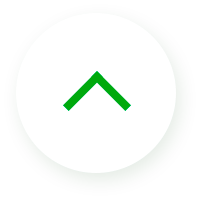


 つながる にぎわう ささえあう
つながる にぎわう ささえあう