本文
おしこめ地蔵(郷柿沢)
むかし、むかし。上市川と郷川との間に、もう一本、川が流れておったそうな。
むかしの話だから、どれくらいの大きさの川だったやらようわからんが、今で言うたら、広野のへんから、郷柿沢の村の方へ流れてきておったらしい。そして、郷柿沢の村の中ほどに、橋が一つかかっておったもんだそうな。
ところで、むかしの人たちは、神さんや仏さんを信じあがめる一方、迷信やまじないなどにたよる心も強かったもんじゃ。とくに、大きい仕事をするとき、たとえば、大きい川に橋をかけるようなときなんぞ、人柱(註1)をたてると言うて、災難などが起こらんように、神さまにお祈りをしたもんじゃと。人柱というたら、生きた人間をそのまんま、橋げたの下などに埋めてしまうことじゃ。それがまた、とくに、若いきれいな娘なんぞがえらばれたそうじゃから、なんともむごい話よのう。
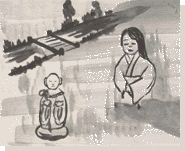 ま、むかしの話はさておいて、今の世になってからのことじゃが、郷柿沢の村の人たちが、あるとき、道路の改修工事のために、むかしの橋のあとらしいところを掘りかえしたんだと。そうしたら、掘りかえされた深い土の中から、お地蔵さんが一体あらわれたもんじゃ。さあ、みんな、おどろきあきれた。
ま、むかしの話はさておいて、今の世になってからのことじゃが、郷柿沢の村の人たちが、あるとき、道路の改修工事のために、むかしの橋のあとらしいところを掘りかえしたんだと。そうしたら、掘りかえされた深い土の中から、お地蔵さんが一体あらわれたもんじゃ。さあ、みんな、おどろきあきれた。
「地面の中に地蔵さんをうめてあったちゃ、こりゃまた、どういうこっちゃろのう。」
あれやこれやと論をしておったが、
「そういえば、おらっちゃ子どものじぶん、こんな話聞いたことあるぞい。」
と、村のお年よりが思い出したんだと。
それは、むかし、この川に橋をかけたときに、村じゅうが相談して、人柱にされるもんはかわいそうじゃ、気のどくじゃと、みんなでちえを出しおうて、生きた人間の代わりに、石の地蔵さまをうめることにしたというのじゃ。
むかしにしてはめずらしい話じゃが、
「きっと、そのときの地蔵さんにちがいなかろう。」
「もったいないこっちゃ。長いこと土の中で、わしらを守っておってくだされたんじゃ。このままにはしておかれんぞ。」
と、村の人たちはさっそく、お堂を建てて、おまつりをしたんじゃと。
そのお地蔵さんは、「おしこめ地蔵」とよばれて、今では村の中ほどの、松本さんの家のそばに、ほかのお地蔵さんらといっしょにまつられてござらっしゃる。
註1 人柱=昔、困難な工事をするとき、神の心をやわらげるために、生きた人を地中に埋めること
石仏の橋地蔵(石仏)
このお地蔵さまは、村の人からはもちろん、付近の人たちからもありがたいお地蔵さまだとあがめられております。
このお地蔵さまのある所は現在の石仏の村の中央で、むかしそこは分岐点になっていました。一方は魚津、滑川方面へ、一方は岩瀬、水橋方面へ、もう一方は上市、立山方面へと分かれる三差路になっていたのです。
お地蔵さまはいつもそこを通る人をながめられ、(どうかぶじに目的地についてくれるように)と、その安全を守っていてくださいました。しかし、その分かれ道を通る者の中には、道をまちがえ迷う者が数知れずありました。そのたびごとにお地蔵さまは悲しい思いで、どうすることもできず困っていらっしゃいました。
ある年の秋、静かな晩のこと。お地蔵さまは、村のあるおばあさんの夢まくらにお立ちになりました。
「わたしはこの村中にある石地蔵の化身である。あの道を通る人々で道をまちがえ、困っている者がたくさんいる。なんとかして救ってやりたいと思う。だから、おまえさんは、村の人たちと相談して、あの地蔵を、川に渡して橋にしなさい。通る人はその石の橋の上に立つと、自分の行こうとする道が頭の中に自然にうかぶであろう。」
と言い聞かせて立ち去って行かれました。
びっくりしたおばあさんが目をさました時には、もうすでに声も聞こえず姿もありませんでした。夜が明けると、さっそくおばあさんは、村の人たちにその話をしました。村の人たちは、みな、
「もったいないことだが、そうさせてもらうか。」
と言い、意見がまとまったので、石のお地蔵さまを分かれ道の川の橋にと渡しました。
それからというもの、道に迷う者は一人もなくなり、村人たちはお地蔵さまのおかげだと言って喜びあいました。
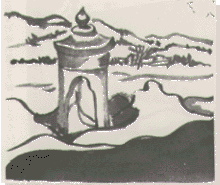 ところが、それから何年かたって、ある人が、材木を家まで運ぶのにその川を利用し、川に材木を流しました。運悪く材木がそのお地蔵さまの橋にぶつかり、石橋はまっ二つに割れてしまいました。石橋は用をなさなくなってしまったのです。
ところが、それから何年かたって、ある人が、材木を家まで運ぶのにその川を利用し、川に材木を流しました。運悪く材木がそのお地蔵さまの橋にぶつかり、石橋はまっ二つに割れてしまいました。石橋は用をなさなくなってしまったのです。
村ではさっそく新しい橋にかけかえましたが、古い割れた石橋は祠に入れて、おまつりしました。それが今あそこに立っている平たい石の橋地蔵さまなのです。
村の人たちは今でも、八月二十四日には旗をたて、地蔵まつりとしてお供え物などをして、感謝の気持ちを表しています。
南町の地蔵堂(南町)
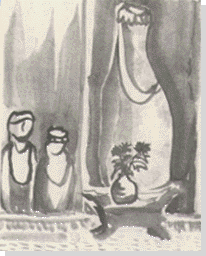 昭和のはじめ、町に釈泉寺伝右エ門という人の家があって、そこにたいへん信心深いおばあさんがいました。ある夜のこと、おばあさんがねていますと、ゆめの中に弘法大師さまがあらわれて、
昭和のはじめ、町に釈泉寺伝右エ門という人の家があって、そこにたいへん信心深いおばあさんがいました。ある夜のこと、おばあさんがねていますと、ゆめの中に弘法大師さまがあらわれて、
「これより西にある南町の地蔵堂に、つえをおいていきます。このつえはわたしが布教(註1)のため、全国を歩いたときにずっと使っていたものです。だれでも願いごとがあれば、このつえをおがみなさい。」
とおっしゃいました。
おばあさんは、ふしぎなゆめを見たものだと思い、さっそく地蔵堂にかけつけたところ、なんと、お堂の前につえがそなえられているではありませんか。
この話が人々に知れわたり、信者がたいへんふえたということです。
また、地蔵堂の中には、お地蔵様とならんで、赤い石がまつってあります。今から八百年ほど前、旭将軍といわれた木曽義仲公が、平家を討つため(くりから合戦)にここを通られたと言われています。その時義仲公がこしをかけて休まれたのが、この赤い石だと言い伝えられ、この石においのりをすれば、おこり(註2)が落ちると信じられています。
註1 布教=宗教をひろめること。
註2 おこり=一定の時間をおいて発熱する病気のこと。別名マラリア。
稗田の魔よけ地蔵(稗田)
今から百五十年ほど前のことです。
毎月三日に開かれる「三日市場」はしだいに繁盛して、近郷近在はもちろんのこと、五百石、水橋、滑川方面、さらに遠くは、飛騨高山からも商人たちが集まって売り買いをしました。
そのころ、このあたり(旧五百石街道)一帯は荒れ川原、荒れ野原で人家もなく、とちゅう狐が出て人をだますと言われていました。買った油揚げが、家に帰って見ると馬糞にばけていたこともありました。ですから、人々はずいぶん心をなやましました。
そこで、とちゅう、今の稗田の地に地蔵さんを安置して、災難のないようにお祈りしたのです。それいらい地蔵さんは、日がくれてから通る人々を見守ってくださると言い伝えられています。
後に、明治のはじめ、ある女の人が旅のとちゅう、夢の中でお告げがあったので、この地蔵さんにいっしんに願いごとをし、塔婆(註1)を大地深く打ちこんだら、やがて願いごとがかなえられたとも言い伝えられています。
また、この地蔵さんはお乳を授けてくださるとも言われ、今でもおとずれて熱心にお祈りする母親を見かけることがあります。
毎月六月二十三日にこの地蔵祭りが行なわれています。
註1 塔婆=供養のために墓に立てる細長い板。
案内地蔵(釈泉寺)
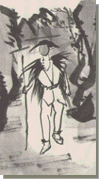 上市川の上流、釈泉寺の村に、ありがたいお地蔵様がおられて、それよりおくの村から町へ出る人たちが、道にまよわないように、教えてくださったそうです。
上市川の上流、釈泉寺の村に、ありがたいお地蔵様がおられて、それよりおくの村から町へ出る人たちが、道にまよわないように、教えてくださったそうです。
たとえば、子どもが一人で、蓬沢から町へ向かって歩いていると、とつぜん、みのを着た人があらわれ、
「わたしのあとについてきなさい。」
と言われます。それで、その人についてゆくと、そのお地蔵様の前まで来たところで、
「ここからは、上市の町まで一本道で、だいじょうぶだよ。」
と言われ、いつのまにか、すがたが消えてしまうのだそうです。
追い討ちの地蔵(稗田)
新屋と稗田を結ぶ道を座主坊道路と言います。その道ばたに地蔵様がまつられているからです。これを「追い討ちの地蔵様」とよんでいます。
そのむかし、弓庄の城がせめおとされた時、城からにげて出たおおぜいの人々を、後ろから追いかけて討ち殺してしまったのだそうです。それいらい、ここを通る人は、いつも後ろから何かにおそわれているような気がして、なんともおそろしいものであったようです。
そこで、人々は、お地蔵さまをおまつりして、その霊をしずめるために供養を続けました。それからは、安心して通れるようになったということです。




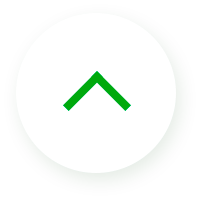


 つながる にぎわう ささえあう
つながる にぎわう ささえあう