本文
あわら田(種)
上市川上流の種は、そのむかし、あわら田のある所として知られていました。
あわら田とは、もと、葦と真菰が生え茂り、荒れはてた泥土の沼田でした。"あわら"とは、「荒れた」「胸まできた」という意味の言葉です。
約百七十年前ごろ、山伏や山法師、江州(今の滋賀県の一部)の武者の子孫などが、いくさをさけて生きぬこうと、方々をさまよい歩いていましたが、そのうちの何人かが、現在の種より約六キロから一〇キロ奥の、小又川の西、後谷あたりに、居を構えました。やがて戦乱がおさまると、しだいに山を下り、現在の種地区に永住するようになりました。そして、だれの助けもかりず、自分たちだけで生きぬくために、耕地を作り始めましたが、とても少なかったので、雑草の生え茂っている沼地を開拓し、あわら、つまり、胸まで泥水につかって稲の植えつけをしたのが、底なしの田んぼ、"あわら田"の始まりだと言われております。
五月下旬から、胸まで沼田につかりながら、まったく浮くようにして、ほとんど鋤を使わず、手で耕しました。六月に入ってから、耕した表面の土を二メートルくらいの竹の棒でならし、田船や足場の竹の丸太を支えにしながら、両手に桶を持って肥料をまき、田植えをしました。これらの作業は、慣れた人でも容易でなく、からだが冷えるため、しばしば風土病になやまされることがあったそうです。
稲刈りは、長さ四メートル、幅三十センチぐらいの板を二枚敷いて、その上にまたがり、刈りながら交互に動かして進みました。田船や丸竹(スキーのようなもの)などを利用して作業を行いました。米の品質、味ともに良かったそうですが、とても困難な耕作方法のため、だんだんすたれていきました。
昭和三十八年、水芭蕉の群生地として知られる高峰山のふもとにある後谷という所から、水芭蕉をあわら田に移植しました。毎年、二百株ずつ、七年間ほどにわたって移植し、今では水芭蕉の咲く沼地として、初夏に訪れる人びとを楽しませています。
磔田(柿沢)
今から四百年ほど前の天正十年(一五八二年)、織田信長が自刃したとの知らせは、またたくまに全国に広がった。
信長を大将として動いていた織田軍の諸将は、そこで活動を停止してしまった。越中松倉城をせめていた前田利家らの連合軍も、松倉の包囲を解いて、それぞれのりょう地へ引きあげていった。こうした急てんで、越中はこぞって、織田軍であった佐々成政に反抗して、上杉景勝に通じ、援軍を求めたという。
しばらく佐々成政についていた、弓庄城主(中新川郡上市町館)、土肥美作守政繁も、佐々成政からはなれて上杉方に乗りかえ、上杉景勝と同盟を結んだ。政繁が寝がえったのをおこった成政は、弓庄城を囲んだ。そして先に人質として成政のところに送られていた政繁の次男、土肥平介(十三歳)を、弓庄城から見える位置に引きすえ、磔にしてしまった
佐々成政としては、政繁が同盟をやぶったみせしめに、平介をきびしい刑にしたつもりであった。ところが、城内のやぐらからこれを見た城兵たちは、平介が殺されたのをあわれに思い、ますます成政に敵意をもやして、死んでも城を守ろうとふるいたったと伝えられる。怒った兵は、城門から出て、平介の屍をうばって城内に引き入れてしまった。
成政の軍は思わぬ抵抗にあって、なかなか弓庄城を落とすことができず、冬になって雪がふってきたこともあって、囲みを解き、兵をまとめて富山城へ引きあげていった。
この、土肥平介処刑の跡は、『はりつけ田』と呼ばれ、弓庄合戦の物語として今も残っている。
花咲く菊石(馬場島)
 早月川の上流の馬場島に、大きな大きな岩がある。長さは十五間(約三十メートル)、幅十間(約二十メートル)、高さはなんと二十三、四間(約五十メートル)もあろうという大きさじゃ。
早月川の上流の馬場島に、大きな大きな岩がある。長さは十五間(約三十メートル)、幅十間(約二十メートル)、高さはなんと二十三、四間(約五十メートル)もあろうという大きさじゃ。
むかしは、秋になるとこの岩の上一面に、色とりどりの菊の花が、美しさを競い、かがやくばかりに咲きみだれておったという。それを見た人は、ただもう夢見心地に、しばらくは動くこともできなんだそうな。
それで人々は、この岩を菊石とよぶようになったということじゃ。
近ごろ、花を見たという話はとんと聞いたことはないが、心がけをよくし、信心をあつくして、花さけ花さけと願いながらくらしておれば、きっといつかはまた見られるようになるかもしれんのう。
神供田(神田)
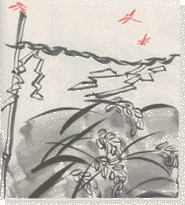 神供田とは、伊勢神宮へ初穂を奉る田のことで、日本のあちこちにありました。
神供田とは、伊勢神宮へ初穂を奉る田のことで、日本のあちこちにありました。
旧弓庄村神田は、もと、五穀の神としてあがめられる「大己貴尊」(大黒様)をおまつりした、神供田のはじめだと伝えられています。
また、この地方が、神様に供える五穀を作ったということから、「神田」という地名ができたともいわれています。
弁慶の足あと(稲村)
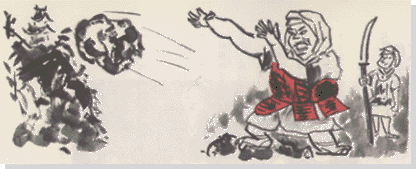
今も残っているそうですが、上市川の上流にある稲村という村に、"久次郎どん"という家があって、その庭に大きな石が一つ、でんと置かれています。その石の上には、人の足あとが残っていました。
それは、あの牛若丸のお話で有名な、武蔵坊弁慶が、稲村へやってきて、近くの城山へ石をほうり投げた時に、
「よいしょ。」
と、ふんばったらできた足あとだと、言い伝えられています。



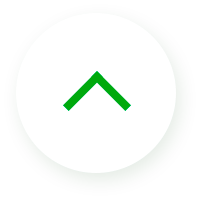


 つながる にぎわう ささえあう
つながる にぎわう ささえあう