本文
千石の保昌どん(千石)
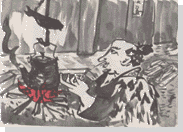 上市川上流のずっとおくに、千石という村がありました。そこに"保昌どん"という家がありました。
上市川上流のずっとおくに、千石という村がありました。そこに"保昌どん"という家がありました。
そのむかし、平井保昌という人がいました。その人は、源頼光とともに、大江山のおにたいじに出かけ、酒呑童子をたいじしたという、勇かんな武将です。保昌どんの家には、今も当時の連判状の写しが収蔵してあると言われています。
広野の方で、盆踊りの時に、かつては、
「一に頼光、二に渡辺よ、三に坂田の金時さまよ、四に椎たけ六郎、五に平井の保昌どんよ、六にろくべい六郎、七に中手の大将殿の七人よ。」
と、うたわれていたそうです。
蓬沢の村で、火種がきれたりした時は、わざわざ山をこえて、年じゅう火種をきらしたことのない、この保昌どんまで、もらい火に出かけたほどのはぶり(註1)だったそうです。
今では、千石の村も、上市川第二ダムの水の下にねむっております。
註1 はぶり=世間がみとめる勢力や人望。
"上市もん"の起こり 加賀の治助
"上市もん"ということばを聞いたことがあるかのう。
これはの、"上市者"の訛った言い方での、よその土地の人が何か事があったときに、上市の者をさして言う呼び名なんじゃ。この呼び名はずいぶんむかしからあったようで、今でも時たま耳にすることがある。よその人が"上市もん"と言うときにはの、「上市の人間ちゃ、なんちゅう偉いもんよ。本当に頼りになる」という尊敬と信頼の気持ちが、もともとはこめられておった。今、もともとは、と言うたんはの、最近では少し違う意味で使われるようになったからじゃ。
ところで"上市もん"とほめそやされるようになったんはいつごろからか、また、どうしてかということは、記録がないから確かなことは分からんがの、明治時代に入ってからの上市消防の、すさまじいまでの働きぶりが大きくかかわっていることだけは間違いなさそうだのう。上市消防はむかしから、それはそれはすばらしかったもんじゃ。
まあ、その消防の話は後でするとして、その前に、どうしても話しておきたい人物がおってのう。それは中村治助という人で、これが上市消防の育ての親とも思えるし、最初に"上市もん"と言われた人ではなかろうかとも思われるんじゃ。
現在、天神町の沢田牧場の近くにいくつか石碑が建っているが、その中に「不動嶽」と書いた碑がある。それが治助の石碑で、生まれは現在の松和町なんじゃ。むかし、江戸末期のころは、松和町から天神町にかけたあたりを、川原町と言うておった。
この人はたいへんな力持ちでのう。体が大きく相撲も強かった。なにしろ五斗入りの米俵を両手に一俵ずつ水平に持って、土俵のまわりを三回もまわったことがある。力自慢だっただけではない。頭もいいし、それに何よりも人情家でのう、弱い人や困っている人を、命がけで助ける義侠心に富んだ人だったんじゃ。
そんな人だったから、加賀の殿様に見いだされて、駕籠かきの親方をつとめておった。また、鳶の親分でもあった。むかしは消防のことを鳶と言うたもんでの。治助の、殿様からのかわいがられようはひととおりではなく、参勤交代で江戸の行き来のときなどは、殿様は駕籠かきが治助でないと安心されんかったほどじゃった。また、まわりのだれからも「加賀の治助」と呼ばれて親しまれ尊敬されておった。ときには、「加賀獅子」と呼ばれて恐れられもしたろうて。
さて、考えてみると不思議なのは、治助は上市の人でありながら、上市の治助と呼ばれないで加賀の治助と呼ばれておったことよのう。それは治助が、加賀藩内だけでなく、遠く、たとえば江戸あたりで有名になっておったからではなかろうかのう。実はそれを裏付けるような話が語り伝えられているんじゃ。
殿様の参勤交代ともなれば、駕籠かきや荷かつぎに必要な大勢の人足を集めねばならん。当時、人足には二とおりあっての、一つは「通し人夫」と言うて、江戸の行き帰りはもちろん、殿様が江戸にいる間ずうっといっしょにいる人足じゃ。治助はこの通し人夫の親方だったわけよのう。もう一つは、宿場ごとに集める「村役人足」で、これは自分の領地内だけ荷をかつぐ。
ところで、村役人足の中にも力自慢、腕自慢がたくさんおってのう、今こそ男を売り出す絶好の機会とばかり、道中、治助に力くらべをいどんでくる者がけっこういたんじゃ。「加賀藩には治助という、江戸に聞こえた剛の者がおるそうな。これさえ負かしゃこのおれも」と、あの手この手と、ときには意地の悪い手まで使ってしきりにいどんでくるのだが、治助にはどうしても勝てんかった。そして、ますます治助の名が、いたるところに広がっていったということよ。
まだほかに、こんな話もある。
さっきも言うたように、通し人夫は、殿様が江戸にいる間一年なり二年なり、国もとの親や妻子と別れて暮らさんならん。人足たちの寝起きする場所は仲間部屋で、退屈しのぎにすることといえば博打と相場がきまったもんで、よその藩の人足たちもしのび込んできて、夜ごと夜ごと鉄火場(博打の場)繰り広げられる。けんかざたもしょっちゅうで、結局は、せっかくいただいた給金もすっからかんになり、やがて国もとへ帰る時には一文なしどころか、逆に借金さえこしらえる者も多かった。治助はこのことを苦々しく思い、なんとか博打をやめさせたいものと思うておった。
そんな治助がある夜、何を思ったか鉄火場に乗り込んで、すすんで博打に加わった。当時は丁半賭博が盛んでの、サイコロをふって丁か半かをあてる博打じゃ。丁は偶数、半は奇数。あたれば賭けたお金が倍になる。はずれればとられる。
治助は丁と張って一両賭けた。みんなはたまげた。一両といえば大金じゃ。それでも、丁と半の賭金がつり合わなければ勝負にならんから、おおかたは半かたにまわった。
いざ、勝負。壷をあけると、サイの目は丁と出た。二回目には同じく丁と張って二両賭けた。また、丁と出た。三回目も丁。四回目も・・・・・・。しまいには全員を相手に回すことになってしもうたんじゃ。みんなは眼がつり上がり、意地になってかかってくる。
治助は言うた。
「いつまでやってもきりがない。勝負はあと一回限りとする。ここに二十両持っている。これを全部賭けるから、おまえら、あり金はたいてかかってこい。」
やがて、「丁半駒がそろいました。いざ、」と声がかかった時、治助は「待て」と制し、すっくと立って小便に行った。人足たちは顔を見合わせ、今の間にと、壷をはぐってみた。案の定、丁と出ていた。だれ言うとなく、「ひっくり返しておけ、半にしておけ。」
そんなことと知ってか知らずか、治助はゆうゆうともどってきた。そして、大きな体をどすんと、地響きたてて座った。勝負の時がきた。治助の賭けは丁。壷が払われた。なんと、サイの目は丁と出ておった。さっきの振動で再びサイコロが、ひょこっと転がったのよ。
みんな青くなって、治助のすごさに震え上がった。やがて真っ赤になった。青くなったり赤くなったり、くやしいやら腹が立つやら。じゃがの、仁王様のような治助にたてつくことなどできたもんではない。しかたなくあきらめてその場を去ろうとした人足たちに、治助は言うた。
「儲けた金は全部返してやる。ただし、国もとへ必ず持って帰ると約束するならばじゃ。約束に背くやつは容赦はせん。」
そして、国の親や妻子がどんな気持ちで帰りを待っているか、それを考えて、今後博打はなるべく慎むようにと、しみじみ説いて聞かせたんじゃ。みんなは頭を垂れて聞き入った。治助のこの度胸の良さ、気っ風の良さに感服し、何よりも熱意に胸打たれない者はなかった。
「ありゃ、どこのもんだい。」と、よその藩の人足たち。
「加賀藩人足頭の治助さんよ。」
「加賀藩は新川郡、上市在の生まれだとよ。」
「偉いもんだのう、上市もんは。」
と、まあ、ここで"上市もん"ということばが出たかどうかは定かでないがの、出ても不思議はないし、だいいち、出たとしたほうが、それこそ我々上市の"もん"にとっては痛快ではないか、のう。とにかく、こういう噂というものは、たちどころに江戸じゅう知れわたるもんじゃ。
さて、やがて時は移り、明治の世になって、藩をなくし代わりに県を置くという廃藩置県のとき、治助は殿様のもとを離れて、故郷の上市へ帰ることになった。その時殿様から、「おまえのその腕と度胸と心意気で、郷里の治安に尽くしてくれ」と、「不動嶽」の名前とともに、纒を一本もろうたんじゃ。その纒は今の消防署にごく最近まであったもんでのう。
上市にもどった治助は、以来、殿様からいただいた不動嶽の名で、鳶として、上市はもちろん、近郷近在のために力の限りを尽くした。同時に若い衆も育て、一家を構えるまでになった。当時治助の家には、治助を慕う二~三十人の屈強な男たちがいつもいたもんでのう、これが火事のときには火の中へ、川があふれれば水の中へ飛び込んで、命がけの仕事をしたもんじゃ。その働きぶりを見て人々は"上市もん"と呼ぶようになったんではなかろうかのう。また、上市に相撲を盛んにしたのも治助の功績よ。
ともかく、これが後に、その名を近郷にとどろかせることになる上市消防のはじまりと考えて間違いなさそうじゃ。
むかしはあっちこっちによう火災があってのう。それもひとつ火がでると、今のようにりっぱな消防施設や武器がないから、またたく間に燃え広がって大火になった。むかしの消防は破壊消防というて、燃え盛る炎の中へ飛び込んで、鳶口一本を頼りに建物を一つ一つぶちこわして火をねじ伏せるやり方じゃった。上市で「竜吐水」という、水鉄砲を大きくしたような手押しポンプを使い始めたのが明治十二年ごろからで、「腕力」という、これも手押しのポンプじゃが、これが二十八年ごろからでの、どちらも今から思えば幼稚なものだが、それでも当時はたいへんな武器になった。
さて、消防の方法がそんな具合だから、どうしても力の強い大勢の鳶が必要になる。上市には明治の初め、すでに百名に近いあらくれぞろいの消防組があったんじゃ。それがいったん火の手が上がると、富山だろうと魚津だろうと、纒を先頭に脱兎のごとくかけつける。火事場へ着けばさっそく、梯子を伝って屋根へ飛び移る者、体に水をぶっかけて猛火の中へ踊り込む者、それこそ水火をいとわずじゃ。大声張り上げ、呼吸を合わせて、みるみるうちに建物をこわしていく。その荒業に群衆は眼を見張ったもんよ。
上市の消防組を見ると、よその組の鳶どもは震え上がったもんでのう。火事になると人々は、早く上市の消防が来ないかと待った。やがて上市から隊を組んで押し寄せると、手をたたいて喜んだもんじゃ。「上市もんが来た。これで火が消える。」と、安堵の胸をなでおろしてのう。やがて火も消え、大仕事をなしとげてゆうゆうと引き上げる勇ましい姿を見れば、"上市もん"の呼び名が高まるのはあたりまえのことよのう。
ところで、この消防組の偉さをいちばんよく知っているのは、なんというても、いつも見ている地もとの者じゃ。上市の子供たちは親から、「やがて大きくなったら、ああいう、世のため人のために尽くす勇ましいもんになれよ。」と言われて育ち、自分でもそうなろうと心に決めてがんばったに違いない。だからこそ後に、上市から、りっぱな政治家や教育者、軍人や商人や相撲とりなど、たくさん出て、"上市もん"の名をますます広め高めていったんじゃ。この心意気は今もしっかり受け継がれている。
終わりに、もう一人、治助にかかわりの深い人物を紹介しようかのう。
それは荒浪というての、これまた体の大きい、相撲のめっぽう強い、それに、なかなかの男まえじゃった。荒浪は治助の一番弟子での、後に治助の跡を継いで荒浪一家を建てた。
明治二十七年、魚津市経田の大火の時に、上市と魚津の鳶同士の間で纒の争いがあって、魚津の鳶に上市側が傷を負わせるという事件が起こった。そして、上市の鳶が一人、魚津方に捕えられたんじゃ。さあ、なんとか魚津と和解して、これを連れもどさんならん。その時、子分どもの心配をしりぞけて、荒浪が一人で乗り込んだ。
そのいでたちは、なんともみごとなもんでのう。上り竜、下り竜の象眼の入った金銀の刺し子のはんてんに、浜縮緬の帯をしめ、人力車にどっかと座って、威風堂々、早月川の対岸を渡っていった。その男ぶりに、立ちはだかる魚津の鳶どもも思はず道を開いて、だれ一人手出しはできんかった。捕えられた子分を無事連れもどしたのは言うまでもないことよ。この時の衣装は今も大切に保存されている。
まあ、これも、「上市もんはのう」と、舌を巻かせた話の一つではなかろうかのう。
荒浪の石碑も、不動嶽の碑と並んで建っておるわい。
村を支えた正印次郎兵衛
正印次郎兵衛という名まえを、これまでに幾度か聞いたことがあるじゃろう。くわしいことは分からぬが、今からおよそ三百五十年ほど前、正印村の名主とか肝煎りとか(註1)いう家がらに生まれなさった人だそうな。
幼いころから心が優しい上に、その利発なことといったら、一を聞いて十を知るほどだったと伝えられておる。
おっ母さんが加賀のお殿様光高公の乳母をしていなさったときのこと、人より二倍も三倍も熱心でねばり強い次郎兵衛は、学問や剣術など、光高公が教わることのすべてをさっさと先取りし、どんどん身につけていきなさったということじゃ。幼心にも光高公に負けたくなかったのであろうのう。
こうして持って生まれた賢さを、さらに自分の努力によって磨きなさってのう、やがて世の中を分けへだてなく見たり、人のために役立とうと、進んで働いたりなさる人になりなさった。
そうそう、その働きの一つに、早乙女川(上市川の旧い名)の大改修という有名な話があったのう。
この早乙女川というのがまた、なかなかやっかいものでのう、大雨が降るたびに氾らんして田畑を水びたしにするしまつ。付近の村々は、二、三年に一度は水害に見舞われておったということじゃ。そのころの早乙女川は今と違うて、極楽寺の方向から丸山下の崖に沿い、稗田、法音寺の中間を通って正印に出、川原田で白岩川と合流しておった。しかもいくつもの分流となっておったから、法音寺や若杉、旧上市村一帯には、特に水害の危険が多くてのう。このことが、村思いの次郎兵衛の大きな悩みの一つとなっていたということじゃ。
たしか、明暦元年(一六四五年)六月のことじゃった。時は梅雨どき。連日の豪雨となった。早乙女川がおとなしくしているはずがない。暴れまくってまたまた大洪水を引き起こしたのじゃ。田植えの後、ようやく根がつき青々とした葉が伸び始めていた田んぼは、一瞬のうちに濁流にのまれ、泥と砂利の下になってしもうた。秋の実りを楽しみに、朝の暗がりから夕星がまたたくまで、汗水たらしてひたすら働いてきた村人たちは、あまりのひどさに体の力がぬけてしもうて、ただぼう然とするばかりじゃった。
気の毒にのう、この年の米の収穫は、いつもの年の半分しかなかったそうじゃ。村の衆の貧しさといったらなかったそうな。腹がへっても食べるものがないのだから、ひもじさこのうえなしよのう。
当時、村役人をしていなさった次郎兵衛は、食うや食わずの百姓たちの苦しみを見るにつけ、ひどく心を痛めなさってのう。なんとしても水害から村を守らねばならんと固く決心しなさった。それからというもの、今まで以上に足しげく村を回って、土地の様子や地形について、熱心に調べなさったということじゃ。
そんなある日、早乙女川が、北島の上の方から急に郷川に切れ込むという出来事が起きたのじゃ。しかも、ひとしきり大水が流れたと思えば、急に水が減ってみたりする。どうもいつもの洪水とは様子が違うのじゃ。不しんに思って現地にかけつけなさった次郎兵衛は、あっと声をあげなさった。それもそのはず、このたびの洪水の原因は柿の木だったからのう。つまり、柿の木が根こそぎ倒れて川をふさいだ形となって水をせき止め、それが一気に郷川へ流れ込んだというわけじゃ。
 この不意の氾らんをじっと見つめていなさった次郎兵衛じゃったが、やがて、新しくできた川の流れ方について調べに行きなさった。
この不意の氾らんをじっと見つめていなさった次郎兵衛じゃったが、やがて、新しくできた川の流れ方について調べに行きなさった。
しばらくして帰ってきなさった次郎兵衛は村人たちに向かって、こう話しなさった。
「皆の衆、今日は柿の木のためにひどいめにあったのう。それにしても、こうたびたび水があふれるようでは、ほんとうに困ってしまうのう。土地は荒れるし、せっかく育てた稲や野菜は流されるし。このままではいくら骨折っても、楽な暮らしなどできはしない。そこで一つ相談だがのう、この早乙女川の川筋を、このさい、思い切って変えてみては。」
「流れを変える、だって。」
「そうじゃ。今日の大水の様子を見てみなされ。せきとめられた水は、新しい川となって郷川へぬけておるのう。これは郷川が早乙女川より低い所にあるからじゃ。つまり、早乙女川と郷川とは合流しやすい状態にあるということじゃのう。早乙女川の川筋を変えることが、最も地の利に合った流れを作ることとなってのう、洪水をくい止め、村を水害から守ることになるのじゃ。」
「たしかに言われるとおりじゃ。そうなりゃあ、湯上野、稗田、正印一帯に、水害の危険が少なくなるのう。」
「ちょっと待ってくだされ。それでは、わしら上市村のものや、川筋の下の村々は困りますわい。今までよりも水害がふえることにもなりかねませんからのう。」
「そうじゃ、そうじゃ。どうでも川筋を変えたいなら、あの白岩川と合流させてほしいものじゃ。」
どちらにも言い分はあるものよのう。特に上市村の百姓たちは、次郎兵衛が何回説得しても、不利な話だとして応じようとせぬ。さすがの次郎兵衛も、今度ばかりはほんとうに弱りなさった。だが、そこは考え深い次郎兵衛のこと。幾日も思案した末に一計を案じなさった。
「さて皆の衆、それぞれの村の実情は、これまでの話し合いでよう分かった。そこで、こうしてみてはどうであろう。北島の上手を基点としてのう、郷川と白岩川までの距離を測るのじゃ。そして、近い方の川と合流させるという方法じゃ。今からさっそく二人の人に同時に出発してもろうて、往復の速さを調べてみることにしよう。早く帰った方が近いという理くつなら、だれにも納得できることだからのう。川の改修工事と言えば、たくさんの土地が必要じゃ。少しでも近い方を選んだ方が、わしらの暮らしを支える田んぼをつぶさずにすむというもの。これで異存はあるまいのう。」
こうして暴れ早乙女川の川筋は、北島地点から、その流れを東に移すこととなり、郷川に沿うて流れるようになったのだと伝えられておる。
当時、村人の中には、次郎兵衛に対して強い反感をもつものもかなりおったと聞いておる。実際のところ、森尻、大永田など川下の村々では、水の危険がたしかに多かったのだからのう。不満が出ても、しかたがないわけじゃ。
しかし、人の営みというものは、長い目で見ていくことが大切じゃ。この早月川の大改修にしても、見方を変えれば、こうもいえるからのう。
つまり、次郎兵衛は、土木師でもあったから、大河川合流によって起きる大型洪水を予想して、上市川と白岩川とを別々にしなさったのかもしれん。また、後々の水枯れのことまで心配しなさって、村々の水の便を図るため、二つの川を引き離しなさったのかもしれん。次郎兵衛は、どれを一番の理由として考えていなさったのか、それは分からぬ。だがわけはどうあれ、わしらの田畑は、こうして今日まで、日照りや水害から守られてきておるのじゃ。ということは、次郎兵衛の働きはそれなりに意味があったということではないかのう。どうじゃ。長い目で見てみると、次郎兵衛は、村の衆の気づかないもっと深いところで、ずっと、村のいしずえとなり、百姓たちを支えていなさったということになりそうじゃのう。
次郎兵衛は、十村(註2)の役をたしか三十年余りも務めなさった。しかも、そのほとんどが郡内に一人しかおかれぬ、ご扶持人十村(註3)であったと聞いておる。ひたすら村を思い、村人と共に生きなさった何よりの証拠よのう。
次郎兵衛が亡くなり、同じく十村役であった息子甚兵衛も亡くなると、そのみたまを、村人たちは、正印村の東、次郎兵衛杉の辺りに、浄福寺を建ててまつったということじゃ。
また、あの白萩農協の乾燥倉庫裏に残されている次郎兵衛のお墓も、村人によって建てられたものだと聞いておる。そのころとすれば、とても大きな墓でのう、地方ではまれにしか見られないものであったそうな。
さらに、次郎兵衛の位牌は、今でも湯崎野の守り神として、大切にされているのじゃ。
何しろ、当時、稗田の草刈り場でしかなかった湯崎野原に、大岩川から水を引き、水田を作れるようにしなさったのだからのう。自分の田んぼがほしくて、この台地の開拓にきていた貧しい百姓たちにとっては、次郎兵衛が神様に見えたのも、当然のことだわい。
稲穂がいっぱい実るこの上市平野はのう、こうして、この次郎兵衛のような、一生かけて働く多くの人たちによって、切り開かれてきたのじゃ。耳をすますと、次郎兵衛や村の衆の歌声が聞こえてくるようじゃのう。
うんこら うんこら うんこらしょ
草刈り台地に水がくる
汗水流して畝つくり
種まきゃ 畑の土が鳴る
よいこら よいこら よいこらしょ
湯崎野荒れ地が田に変わる
米のまんまも夢じゃない
ひと鍬ごとに 腕が鳴る
よいやさ うれしや ありがたや
湯崎野台地に稲穂がたれる
夢かうつつか この恵み
黄金の波に 胸が鳴る
註1 名主・肝煎り=百姓の取りまとめ役、庄屋さまのこと。
註2 十村=十か村ていどを受け持つ村長のような役。
註3 ご扶持人十村=郡内に一人おかれ、当時の新川郡十三組の十村のかんとくをする地位。



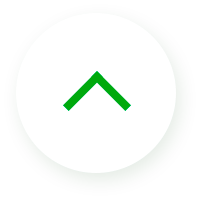


 つながる にぎわう ささえあう
つながる にぎわう ささえあう